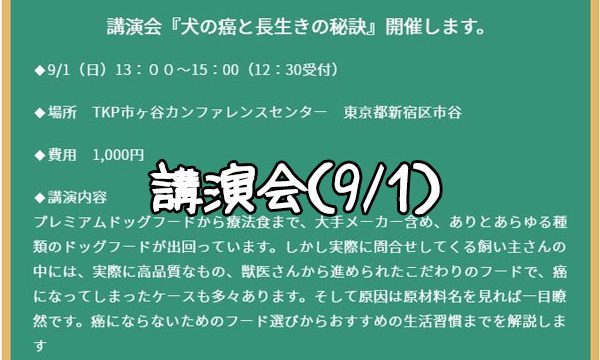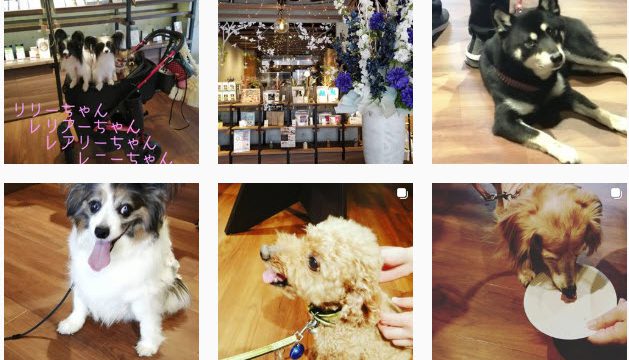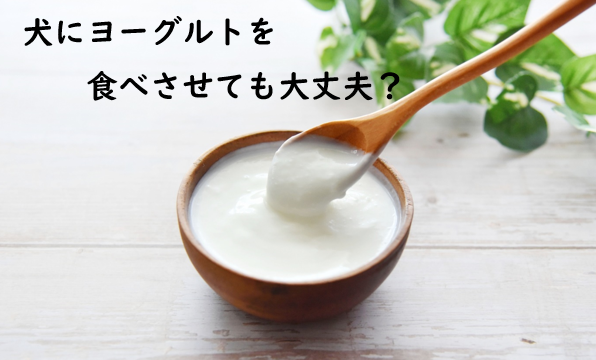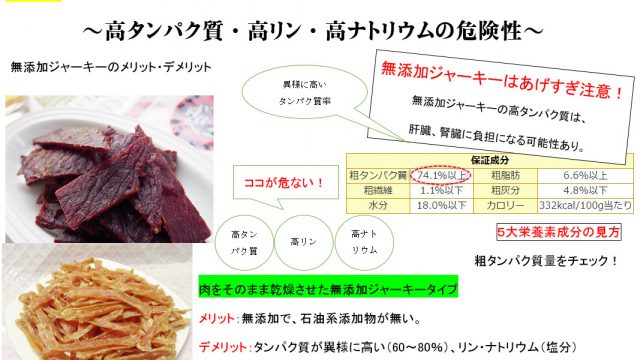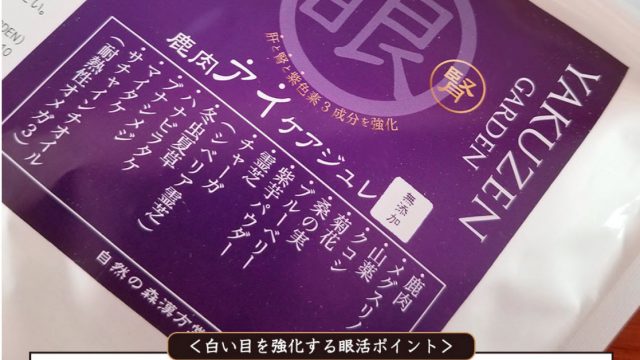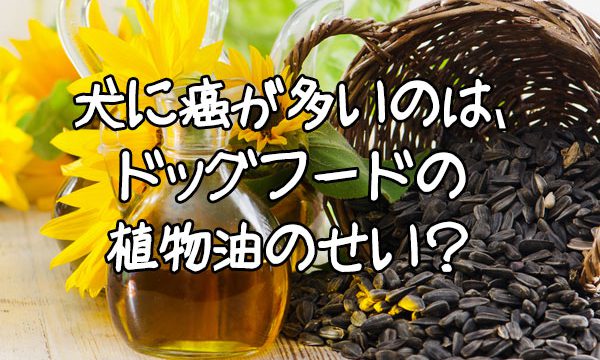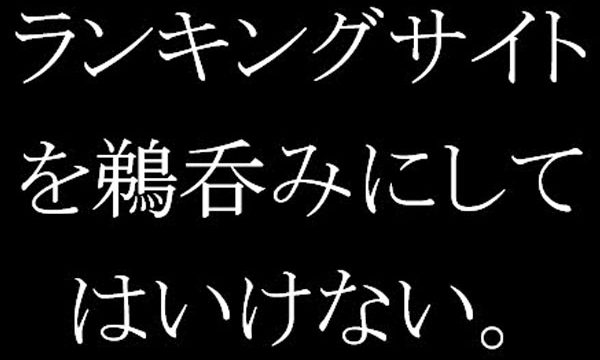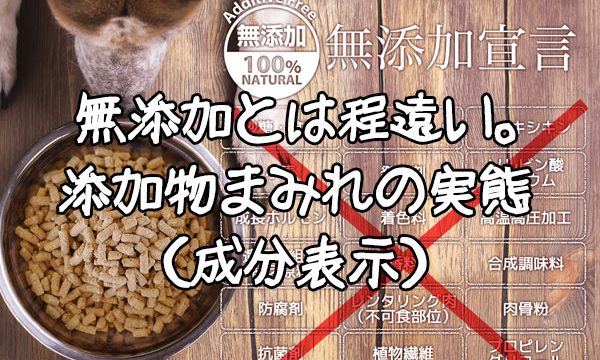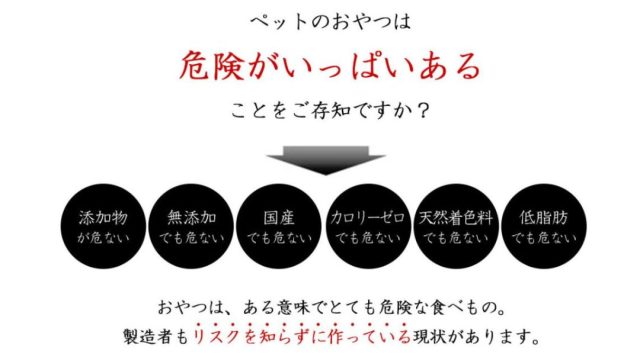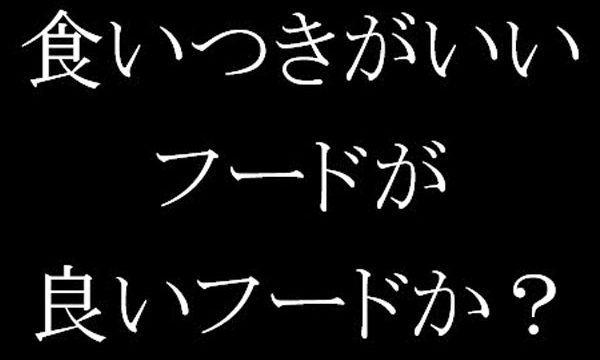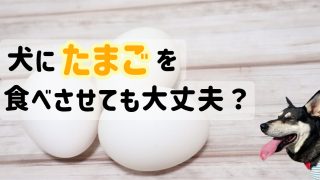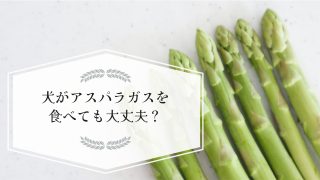Contents
秋から冬にかけて旬を迎えるりんごは、手軽に手に入る果物として日本の家庭で親しまれています。美味しく、手軽なりんごを愛犬にも与えたいと考える飼い主さんも多いのではないでしょうか?しかし、りんごを愛犬に与える際には押さえておくべきポイントがあります。本記事では、犬にリンゴを与えるメリットや注意点、具体的な与え方を解説していきます。
基本的に犬はりんごを食べても平気

基本的に犬にりんごを与えるのは問題ないです。しかし、りんごに含まれている果糖の糖質で血糖値が上がる可能性や腎臓病など内臓疾患によっては、カリウム制限をした方が良いケースもあり、時と場合によってはデメリットになるケースもあります。与える量やあげ方に注意が必要です。
犬がりんごを食べ始めて良いタイミング

犬は基本的に年齢関係なくりんごを食べても問題ありません。りんごの甘みは多くの犬に好まれ、ほんのり甘く、胃にもやさしいです。すりおろしたりんごは、人間の赤ちゃんの離乳食としてはもちろん、生後1カ月ほどの子犬の離乳食としても利用できます。
ただし、消化器官の機能が未熟な子犬に一度に大量に与えると、果糖による血糖値上昇や食物繊維の過剰摂取による軟便が起こる可能性があります。そのため、最初は少量から始め、段階的に増やすことをお勧めします。愛犬の大きさに応じて与える量を調整しましょう。
犬にりんごを与える4つのメリット

メリット① 食物繊維(ペクチン)を摂取できる
りんごには、ペクチンと呼ばれる水溶性食物繊維が含まれています。ペクチンは腸内に蓄積した不要物を排出する助けになり、整腸作用が期待されます。
さらに、ペクチンは腸内の有害な細菌を減少させ、有益な細菌を増やす働きがあるため、腸内環境の改善に繋がります。これにより、便秘や軟便の解消が期待されます。
また、腸内環境の改善は免疫力の向上にも繋がる可能性があります。りんごのペクチンは犬の腸の健康をサポートする重要な役割を果たします。
メリット② リンゴ酸・クエン酸を摂取できる
りんごには「リンゴ酸」と「クエン酸」が含まれており、これらは体内の代謝を促進し、体内に蓄積した乳酸の分解を手助けします。したがって、運動後に愛犬にりんごを与えることで、疲労回復をサポートするのに役立つと考えられます。適切な量で与えることで、愛犬の健康をサポートできるでしょう。
メリット③ カリウムを摂取できる
りんごにはカリウムというミネラルが豊富に含まれています。カリウムは浸透圧を調整し、体内に蓄積した塩分を尿とともに排出する役割があり、血圧の上昇を防ぐ他、神経伝達や筋肉収縮に繋がります。
ただし高齢や腎臓病の状態では、腎臓の機能が低下し余分なカリウムを適切に排出できなくなるため、「高カリウム血症」と呼ばれる症状が起こる可能性があります。高カリウム血症はけいれん、頻脈、不整脈などを引き起こす原因となり、最悪の場合、命にかかわることもあります。したがって、シニア犬や腎臓病の犬、心臓の機能が低下している犬にりんごを与える際は慎重に注意する必要があります。
メリット④ ポリフェノールを摂取できる
ポリフェノールには強力な抗酸化作用があり、病気の予防や老化防止に繋がる可能性があります。リンゴの皮には多くのポリフェノールが含まれています。そのため、皮のまま犬に与えることで、より多くのポリフェノールを摂取できます。また、最近の研究では、ポリフェノールが筋肉の強化や脂肪の減少に効果がある可能性が示唆されていますが、犬に対する具体的な効果についてはまだ定かではないです。
犬にりんごを与える際の注意点

市販のりんごジュースやりんごジャムは糖質を多く含むので注意する
りんごジュースなどの加工品は、愛犬ちゃんにとって多すぎる糖質が含まれています。糖質の摂りすぎは肥満の原因になりますし、糖質はブドウ糖に分解され、継続的な使用は腫瘍の餌にもなる可能性があるため、シニア期、または病気の愛犬には、あげない方が無難です。与える場合には、お水や茹でた野菜等をミックスし、りんごの糖質を薄めてあげるといいでしょう。
アレルギーに注意する
犬にリンゴを与える際は、リンゴアレルギーに注意しましょう。アレルギーは体の免疫機能がタンパク質に対して異常反応を示すことで発生します。
リンゴにもわずかですがタンパク質が含まれており、これがアレルギー反応を引き起こすことがあります。アレルギー反応が起こると、下痢や嘔吐、痒みなどの症状が見られることが多いです。
犬に初めてリンゴを与える場合は、量を少なくして、他の新しい食べ物は避けるようにしましょう。これにより、アレルギーが発生した場合に重症化を防ぎ、原因を特定しやすくなります。
りんごの種や芯に含まれる「シアン化合物」に注意する
りんごの種や芯、葉、茎にはアミグダリンと呼ばれるシアン化合物が含まれています。アミグダリンは無毒ですが、大量に摂取すると消化する過程で有毒なシアン化水素が生成されるため、中毒のリスクがあります。そのため、りんごの実以外の部分は犬に与えないようにしましょう。
中毒の症状には、りんご摂取後3時間以内に呼吸困難やけいれん・嘔吐・下痢などを引き起こす可能性があるため、りんごの与え方には充分な注意が必要です。りんごを与える際は、種や芯、葉、茎を取り除いて安全に提供してください。
特定の持病がある犬には与えない
心臓や腎臓に持病がある犬にはリンゴを与えないようにしてください。リンゴに含まれるカリウムは、これらの病気を持つ犬には制限すべき成分です。特に療法食を食べている犬の場合、リンゴを与える前には必ず獣医師に相談することが重要です。
皮を剥く必要はないがよく洗ってからあげる
りんごの果皮には農薬が付着していることがあるため、微量であっても小型犬には有害な影響を及ぼす可能性があります。与えるリンゴが無農薬や有機栽培でない場合、りんごの皮を剥いてから与えるか、もしくは十分に洗ってから与えましょう。農薬の残留物を最小限にすることで、愛犬の健康を守ることができます。
犬への適切なりんごの与え方

量
りんごは食事の代わりにはなりません。おやつとして与える分には良いでしょう。ただし、りんご単独で与えるより、水や茹で野菜とミックスした状態であげるのが理想的です。
また、おやつとして与えた場合は、1日に必要なカロリーの10%程度に留めるべきと言われています。このカロリーから計算すると、与えて良い目安量は以下のようになります。
・小型(2~5kg) 34g~67g(中1/6個~中1/3個)
・中型(6~15kg) 77g~153g(中1/3~中5/6個)
・大型(20~50kg) 189g~376g(小1個~中1.5個)
上記は健康な犬の場合の目安であり、腎臓や肝臓病など、内臓疾患の場合には、もっと少なくした方が良いでしょう。
与え方
犬にリンゴを与える際は、皮に汚れや農薬が残っている可能性があるため、よく洗ってから与えましょう。皮は細かく切って構いませんが、種と芯は取り除いてください。また、大きな塊で提供すると、食道に詰まる恐れや消化不良のリスクがあるため、小さく切って与えましょう。
りんごの果糖の害を軽減させるために
りんごはGI値の低い果物ではありますが、果糖が含まれています。そのため血糖値が上がる可能性、ブドウ糖に変換されるデメリットがあります。少量であれば、 あげても大丈夫です。
【基準】
高GI値:61以下
低GI値:60以下
リンゴのGI値:36
ダイエットが必要な場合や、糖尿病の愛犬ちゃんには、りんご単独ではなく茹でた野菜と一緒に与えることをおすすめします。
食物繊維で果糖を薄めることができますし、余分な果糖を絡みとり、排出する働きがあるため、より果糖のデメリットを排除できるという点で有効です。ゆでた野菜で食物繊維を作るレシピは以下の通りです。
◆サキニコブ(血糖値を上げにくい野菜)
さつまいも・きのこ・人参・小松菜・ブロッコリー
いずれも必ず細かくみじん切りし、3~10分茹でて、ゆで汁は捨てましょう。※焼く、蒸す、レンジはNG
糖分や不要な栄養成分が流れ出ているゆで汁を捨てる事が大切です。
・フード:ゆで野菜:りんごの割合=1:1:1 または 2:1:1
特にシニア期や内臓疾患のある犬猫ちゃんにはこの様な工夫をしてあげると無難でしょう。
りんごの与え方のまとめ
与える場合には、種・芯・葉・茎は取り除き、皮はよく洗って小さくカットしましょう。
初めて与える時は少量にとどめ、愛犬の様子をよく観察して、体質・状態に合わない場合には与えるのを控えましょう。また、果糖のデメリットを薄める場合には、ゆで野菜を1:1で混ぜて与えるのがお勧めです。
糖質が気になる愛犬ちゃんにも安心なおやつ
和漢のおやつシリーズは低糖質で、甘味料として血糖値を上げにくい羅漢果を使用しています。内臓に負担をかけずに美味しく食べられるサプリ感覚で身体の健康維持をサポートし、食感の違いで飽きさせません。
まとめ

手軽に手に入り、犬にとって栄養価も高いりんごは、甘い香りとシャリシャリとした食感で多くの愛犬が喜びます。これらの特性から、おやつとして与えるのに適した果物です。
生で与える場合には少量で留める。
果糖(糖質)の害を中和させるために同量のゆで野菜と一緒に摂る
おやつとしての適量を守って、与え過ぎには注意しましょう。