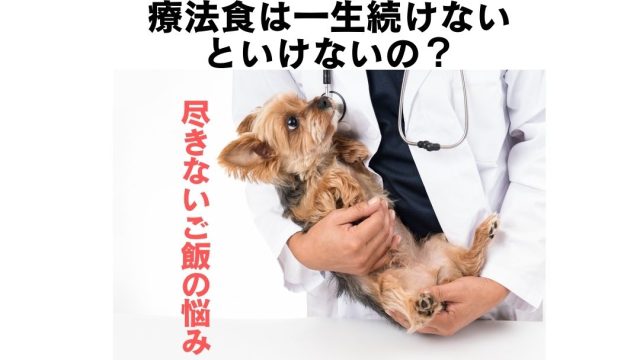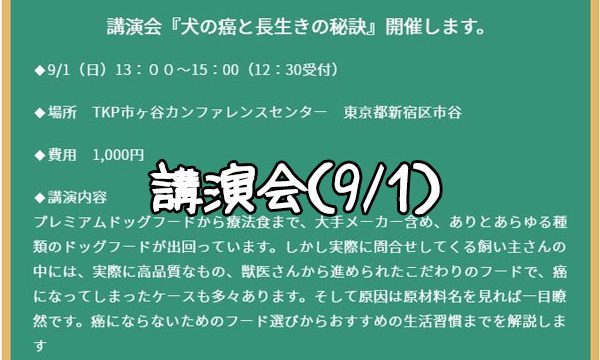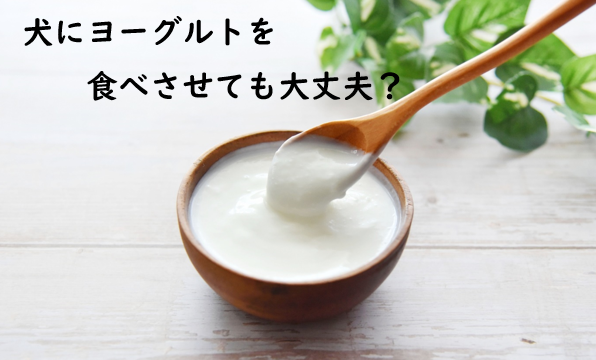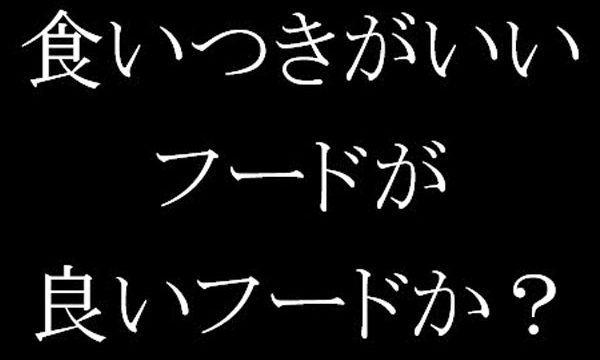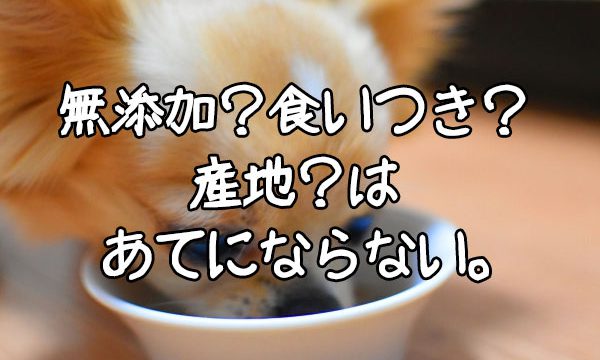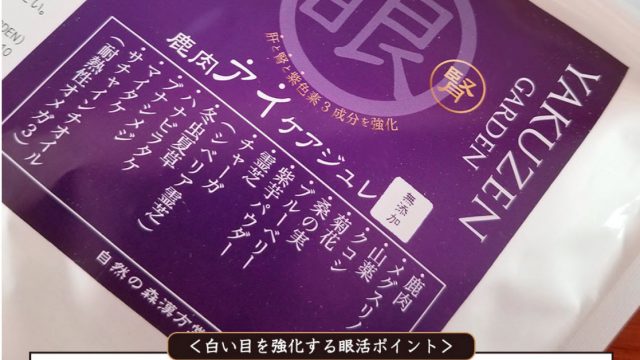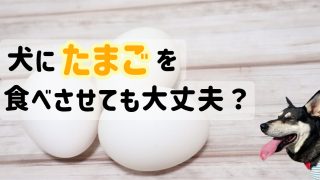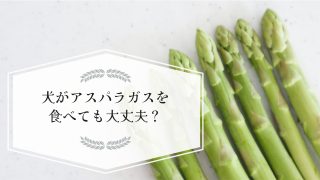犬を飼っていると、時々愛犬のよだれが気になる瞬間があるかもしれません。私たち人間も、美味しい食べ物が目の前にあると、ついついよだれが垂れそうになることがありますよね。実は犬も同じで、普段よりも多くよだれを垂らす場合、健康に何かしらの問題を抱えている可能性があります。
そこで本記事では、犬がよだれを垂らす理由と、注意が必要なよだれの兆候を解説していきます。「最近愛犬のよだれが多いな」と感じる方は、ぜひ参考にしてください。
犬がよだれを垂らす6つの理由・原因

犬がよだれを垂らす主な理由は以下の6つです。
- 空腹だから
- リラックスしているから
- 苦味や刺激を感じたから
- 暑いから
- ストレスを感じているから
- 病気・体調不良だから
それぞれの理由について詳しく見ていきます。
理由1. 空腹だから
空腹時に食事を前に座っていたり、食べ物を待っている間に犬のよだれが増えるケースがあります。これは食事の消化を助ける準備としての自然な反応なので、特に心配する必要はありません。
理由2. リラックスしているから
寝ている時、飼い主さんと一緒にくつろいでいる時など、リラックスしているときは副交感神経が優位になり、口の中を潤すため、サラサラした唾液が増えてよだれを垂らすことがあります。
理由3. 苦味や刺激を感じたから
洗剤や苦い薬など刺激物を舐めたり飲んだ後、犬のよだれの量が増加することがあります。これは、口内の苦味や刺激に対応してよだれが多く分泌されるためであり、心配する必要はありません。十分な量の水や食事を与えることで犬は落ち着くでしょう。万が一、洗剤などを舐めてしまった場合は、速やかに獣医さんに診察してもらいましょう。安全のために専門家のアドバイスが必要です。
理由4. 暑いから
人間のように汗をかいて体温調節ができない犬は、暑くなると、体の熱を放熱させるために口を開けて舌を出して呼吸をします。この時吐き出した息と一緒に、口の中の唾液が気化することで、体温を下げることができます。ただし、口が開けっ放しになってしまうため、よだれが垂れやすいです。
理由5. ストレスを感じているから
動物病院や行ったことのない公園など不慣れな場所では、犬のストレスや緊張が増すことでよだれの量が増えます。また、震えや荒い呼吸などの症状もストレスの兆候かもしれません。雷や台風の際も犬のよだれ量は増える傾向にあります。
また、愛犬が不安や緊張を感じている場合、原因を排除するのが最善ですが、難しい場合は、お気に入りのおやつやおもちゃを使ってリラックスさせることができます。
理由6. 病気・体調不良だから
様々な健康問題が原因で、犬のよだれの量が増えることがあります。以下のようなケースでは特に注意が必要です。
- 口内炎
- 歯周病
- 喉頭炎
- 胃炎
- 胃膨張
- 熱中症
- てんかん
- 誤飲
他にも口臭、食欲不振、発熱、痙攣、吐き気などの症状があれば、迅速に動物病院を受診しましょう。
犬のよだれで考えられる8つの病気

犬のよだれで考えられる8つの病気は以下の通りです。
- 歯周病・歯肉炎
- 熱中症
- 口内炎
- 胃炎・誤飲
- 口腔内腫瘍
- てんかん
- 咽頭炎
それぞれの病気について見ていきましょう。
1. 歯周病・歯肉炎
歯周病や歯肉炎の時には、よだれの量が増える他にも以下のような症状があります。
・歯肉が赤く腫れる、出血や膿が出る
・歯石がついている
・口臭がきつくなる
・フードを食べにくそうにしている 食欲が落ちる
・口を気にする、必要以上にこする
・くちゃくちゃと音を立てている
他にも、口の様子がいつもと違っていたり、吐き気を催すこともあります。
2. 熱中症
犬がよだれを垂らす際は、熱中症の可能性も考えられます。湿度や気温が急上昇すると、犬の体温も急激に上昇し、犬は体温調節が追いつかずに熱中症になってしまいます。
熱中症になると、多量のよだれを放出するだけでなく、呼吸が急に荒くなり、舌や口の内部が赤くなることがあります。また、嘔吐や下痢などの症状も出ることがあるため、このような場合は速やかに獣医の診察を受ける必要があります。適切な治療が遅れれば、状態はさらに悪化し、最悪の場合、命に危険を及ぼすこともあります。
3. 口内炎
口内炎は口の中の粘膜に起こる炎症の総称で、発生する場所によって名称が異なり、例えば歯肉炎も口内炎の一種です。原因は多岐にわたりますが、よだれ以外にも食欲不振、口臭、強い痛みなどの症状が現れることがあります。痛みがあると、口を触られるのを嫌がる、あくびを途中でやめてしまう、などの様子が見られます。
よだれもいつもよりドロッとしていたり、血が混ざったよだれが出てくることもあります。
4. 胃炎・誤飲
よだれ以外に吐き気が観察される場合、胃の炎症や、異物を誤飲してしまう恐れがあります。異物誤飲の場合、誤って摂取したものが有毒か鋭利なものである場合、迅速な対処が必要です。その場合、すぐに獣医の診察が緊急に必要となります。早急な対応が愛犬の安全につながりますので、すぐに動物病院を受診しましょう。
5. 口腔内腫瘍
口腔内腫瘍には良性と悪性のものがあります。悪性の口腔内腫瘍は痛みを引き起こすこともあり、口を閉じづらくなることでよだれが多くなりがちです。また、よだれ以外にも食事量が急に減ってくる、歯茎や口まわりからの出血、口臭がひどくなるなどの症状が現れます。
6. てんかん
てんかんは脳に関連する疾患で、一般的に「てんかん発作」として知られる症状が現れます。てんかんの発作前徴候として、よだれが増えることがあることがあります。また、舌を舐めたり、不安定な行動を示し、ウロウロと歩き回ることもあります。てんかんの発作が発生した場合、その症状を記録し、状態が安定したら動物病院で獣医に相談しましょう。早期の診断と適切な治療が、愛犬の健康を左右することになります。
7. 咽頭炎
咽頭炎は、食道の入り口や気管の入り口が炎症を起こしている状態を言います。
原因としては、ウイルス・細菌などの感染のほか、タバコの煙や車の排ガスなどの有毒物質の吸引や誤飲による傷、腫瘍などが考えられます。症状のひとつとして大量のよだれがあり、その他に喉やリンパの腫れ、咳、呼吸障害などもみられます。
8. 中毒
中毒症状が発生した場合、犬は多量のよだれを垂らすことがあります。例えば、チョコレートやネギ類を誤って食べた場合、中毒症状としてよだれや痙攣が現れることがあります。犬にとって危険な食べ物は多く、特にチョコレートに含まれるカカオは誤飲した際に過剰な興奮作用を引き起こし、よだれや痙攣を引き起こす可能性があります。
病気の可能性があるよだれを見分ける3つの方法

1. よだれがポタポタと止まらない
単によだれが多いだけでなく、異常な量のよだれがポタポタと止まらない場合は、病気の可能性があり注意が必要です。
・熱中症
・胃拡張・胃捻転など
・乗り物酔い(車酔い)など
極度の緊張、恐怖などのストレスを感じている場合でも、よだれが止まらなくなる場合があります。思い当たる原因がない、よだれの他に症状が出ている場合は、動物病院で受診しましょう。
2. 気泡を含んだよだれになっている
よだれに気泡が含まれている場合、下記の可能性があります。
・愛犬が誤って殺虫剤や農薬などを飲み込んでしまった
・脳の異常
・肺などの呼吸器や心臓の疾患
・胃拡張・胃捻転など
・乗り物酔い(車酔い)など
・膵炎
原因が明らかでなければ、命にかかわる病気の可能性もありますので、早めに動物病院で受診しましょう。
3. よだれから臭い匂いがする
よだれから臭い匂いがする場合、特定の病気の可能性が考えられます。
例えば、口からアセトン臭がする場合、糖尿病の可能性があるかもしれません。糖尿病の場合、口渇が原因で口臭が生じることもあります。
また、アンモニアのような臭いがある場合、腎不全や尿毒症の兆候かもしれません。これは、体が毒素を適切に排出できないために悪臭が生じることがあります。
さらに、酸っぱい匂いが感じられる場合、胃腸炎や胃酸の過剰分泌の可能性が考えられます。嘔吐や下痢などの症状が同時に見られる場合、胃腸の問題が疑われます。臭いだけでなく、血が混じったよだれや粘りのあるよだれも、病気の兆候として考えられますので、早めに動物病院を受診しましょう。
ホルモンバランス維持におすすめフード・サプリ
健康的なホルモンバランスを維持するために、脂質、炭水化物、食物繊維を理想的な比率バランスで配合設計した和漢植物シリーズ
◆マウスクリーンパウダー
◆和漢みらいのドッグフード 特別療法食 栄養回復(G・A・N+)
◆和漢みらいのドッグフード 特別療法食TO(糖尿病・白内障用)
◆和漢みらいのドッグフード 特別療法食J(腎臓用)
◆和漢みらいのドッグフード 特別療法食IC(胃腸・消化器用)
まとめ

今回は、犬がよだれを垂らす理由と、考えられる病気、病気の見分け方について解説していきました。犬がよだれを垂らす際、基本的には問題ないケースが多いですが、中には病気の兆候であることもあります。
万が一、病気の可能性があるよだれの垂らし方をしていた場合、速やかに動物病院に診てもらいましょう。