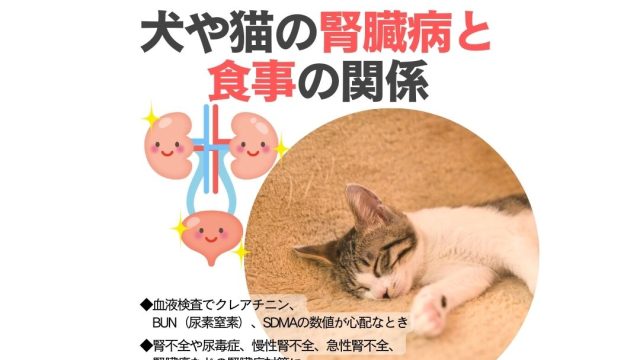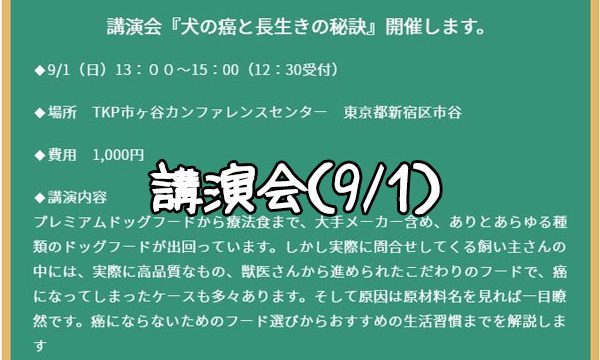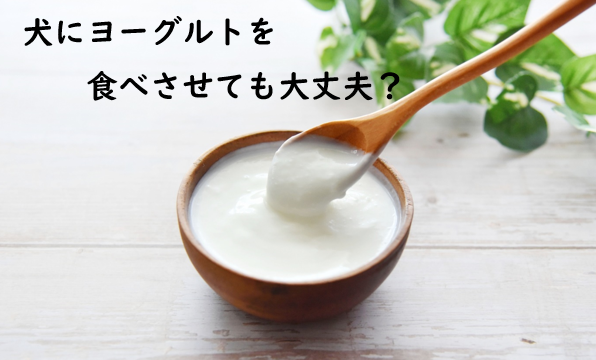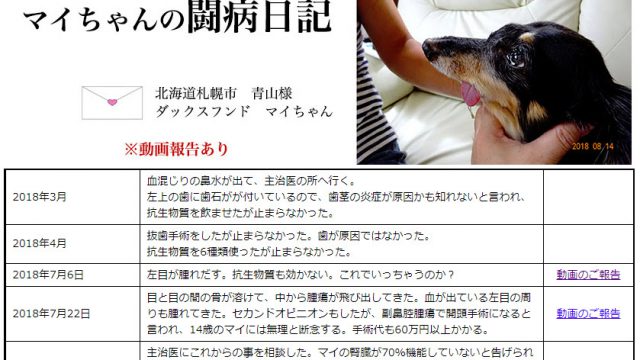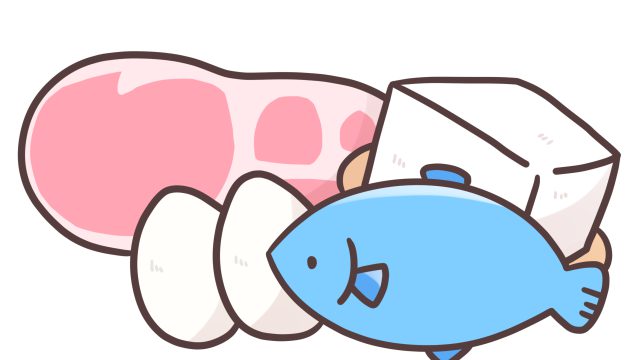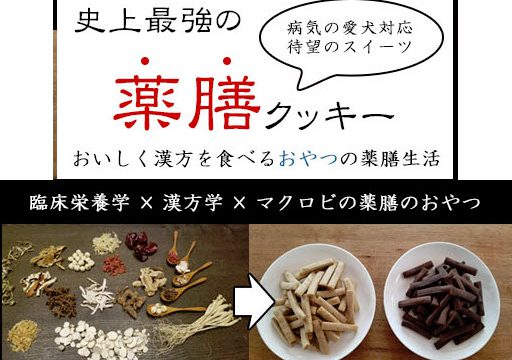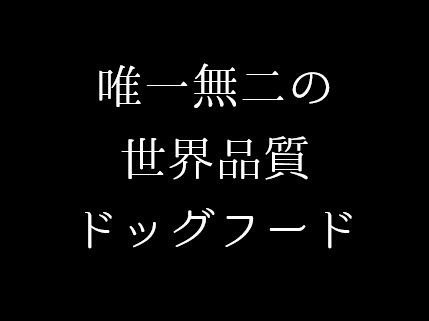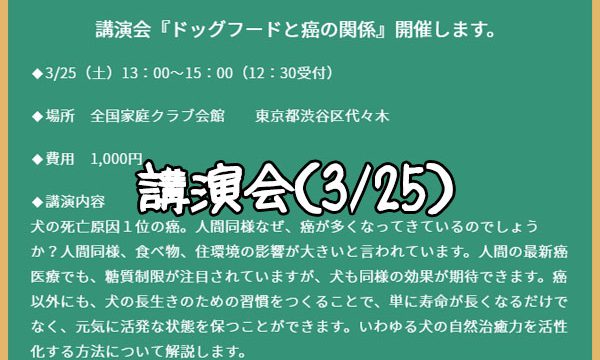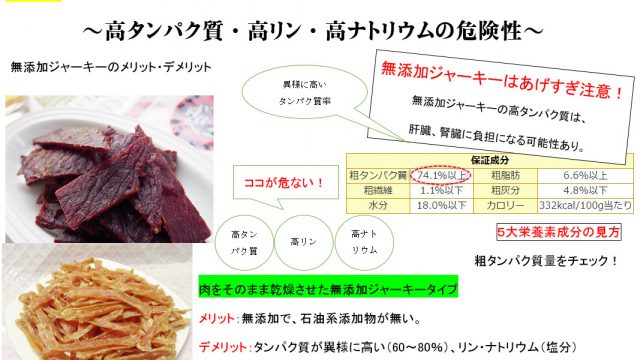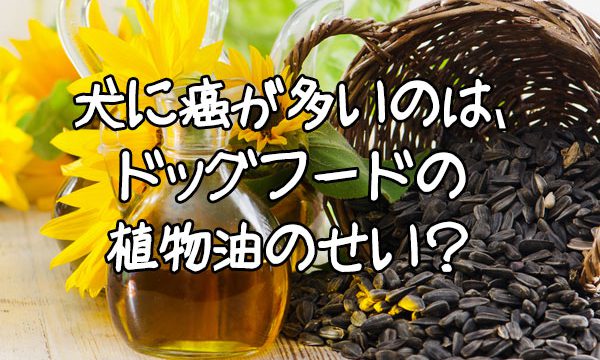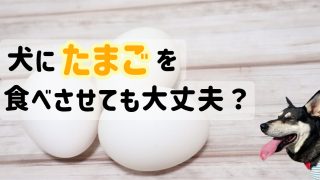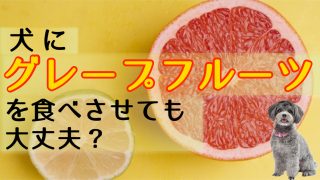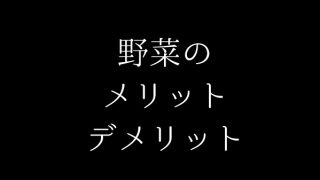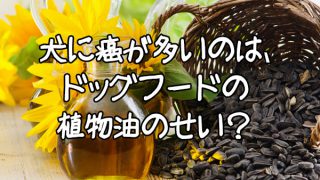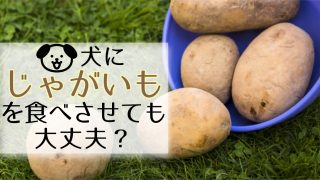Contents
犬も人間の様にあくびをしますね。単に眠いという理由だけでなく、なかには深刻な理由であくびをしている場合もあるので、そのあくびの意味を見極めることが大切です。そこで今回は、犬があくびをする理由や意味、対処法について解説します。
犬があくびをする5つの理由・原因

理由1. 眠いから
犬も人間と同様に、眠い時に生理的なあくびをします。脳に酸素を送るためという説や、あくびによって体温調節をして脳のオーバーヒートを防ぐためなど、さまざまな説があります。しかし、どうして眠いときにあくびが出るのかという理由は、まだはっきりとはわかっていません。
理由2. 他の犬や人間のあくびが伝染したから
人間同士で、なぜか友人があくびをしたら、つられて自分もあくびが出た、という経験はありませんか?この「共感あくび」は、見知らぬ人よりも親密な関係にある飼い主さんからうつることが多いという研究結果があり、信頼関係を表すサインとも言えます。特に、人と犬の絆が強いほど伝染しやすいようです。
理由3. リラックスしたいから
緊張を和らげて、リラックスしたいというサインです。
緊張したときやストレスを感じたときなどに、気持ちを落ち着かせるための「カーミングシグナル」(犬同士のコミュニケーション方法)として、あくびをすることがあります。カーミングシグナルとは、「カーミング=落ち着かせる」「シグナル=合図」という意味で、自分や相手を落ち着かせるために犬が見せる行動のことです。犬が初めての場所や動物病院に行ったとき、いたずらをして叱られているときなどによく見られます。
もともと集団で行動していた犬は、“平和”を好む動物。あくびをすることで、自分の気持ちを落ち着かせるのはもちろん、相手に対して敵意や争うつもりがないことをアピールし、不要な争いごとを避けようとしているのです。
理由4. ストレスを感じているから
犬は不快感を抱き、強いストレスを感じている時もあくびをします。病院など苦手な場所に行った時や知らない人に触られている時、あくびをしている愛犬を見た事はありませんか?これは、相手に「止めて欲しい」と訴えている場合もあるので、愛犬の表情を見極めつつ、対処してあげましょう。
理由5. 病気・体調不良だから
急にあくびが増えたり、体調が悪いような素振りを見せたりしたら、それは体調不良や病気のサインである可能性があります。
あくびのときに以下のような症状や行動が愛犬にみられる場合は、病気や体調不良を疑い、獣医師などに相談することをおすすめします。
・あくびの回数が異常に多い
・あくびの後に顎をガクガク・カタカタと震わせる
・口を大きく開けてあくびができない
・舌や歯茎の色が普段の色とは違う
・口の中がいつもより臭う など
犬のあくびで考えられる5つの病気

以前と比べて明らかにあくびの回数が増えた、見るたびにあくびをしているなどの変化があらわれた場合は、注意が必要です。
1. うつ病
犬は言葉を話せないので実際の心の内はわかりませんが、人間と同じように、強いストレスを長期間にわたって感じると、うつ病を発症することがあります。うつ病になると食欲不振になる、元気がなくなる、自傷行為を繰り返すなどに加え、あくびが多くなります。
2. 低血糖症
低血糖症は血液中の糖分濃度が低くなった状態です。低血糖によって脳の働きが低下するため、脳へより多く酸素を送り込もうと、あくびの回数が増えることがあります。低血糖症は子犬や小型犬に多いと言われています。
3. 貧血症
貧血になると身体の中に酸素を運ぶ機能が低下するため、酸欠状態になり、酸素をより多く取り入れようとしてあくびの回数が増えることがあります。あくびだけでなく、舌や歯茎の色が白っぽく見える場合は、貧血になっている恐れがあるので、すぐに動物病院を受診しましょう。
4. てんかん
てんかんは、脳神経に異常な電気信号が発生し、発作をくりかえす脳の病気です。
発作時の症状として、全身が突っ張る、手足をバタバタさせる、落ち着きがなくなる、よだれがたくさん出る、遠吠えのような声を出す、顎がガクガク震えるなどの他に、あくびもよく見られます。また、てんかんの発作の予兆としても、あくびが見られる場合があります。
5. 歯のトラブル
歯周病や歯肉炎など、口腔内の痛みや歯の不快感で、口の開け方がいつもと違うようなあくびが見られます。痛みを伴うので、あくびの途中で鳴いたりすることもあります。
あくびだけでなく、口を気にするそぶりや、ご飯を食べにくいなどの症状があるかどうかも気をつけましょう。
犬のあくびで病気かどうか見分ける4つの方法
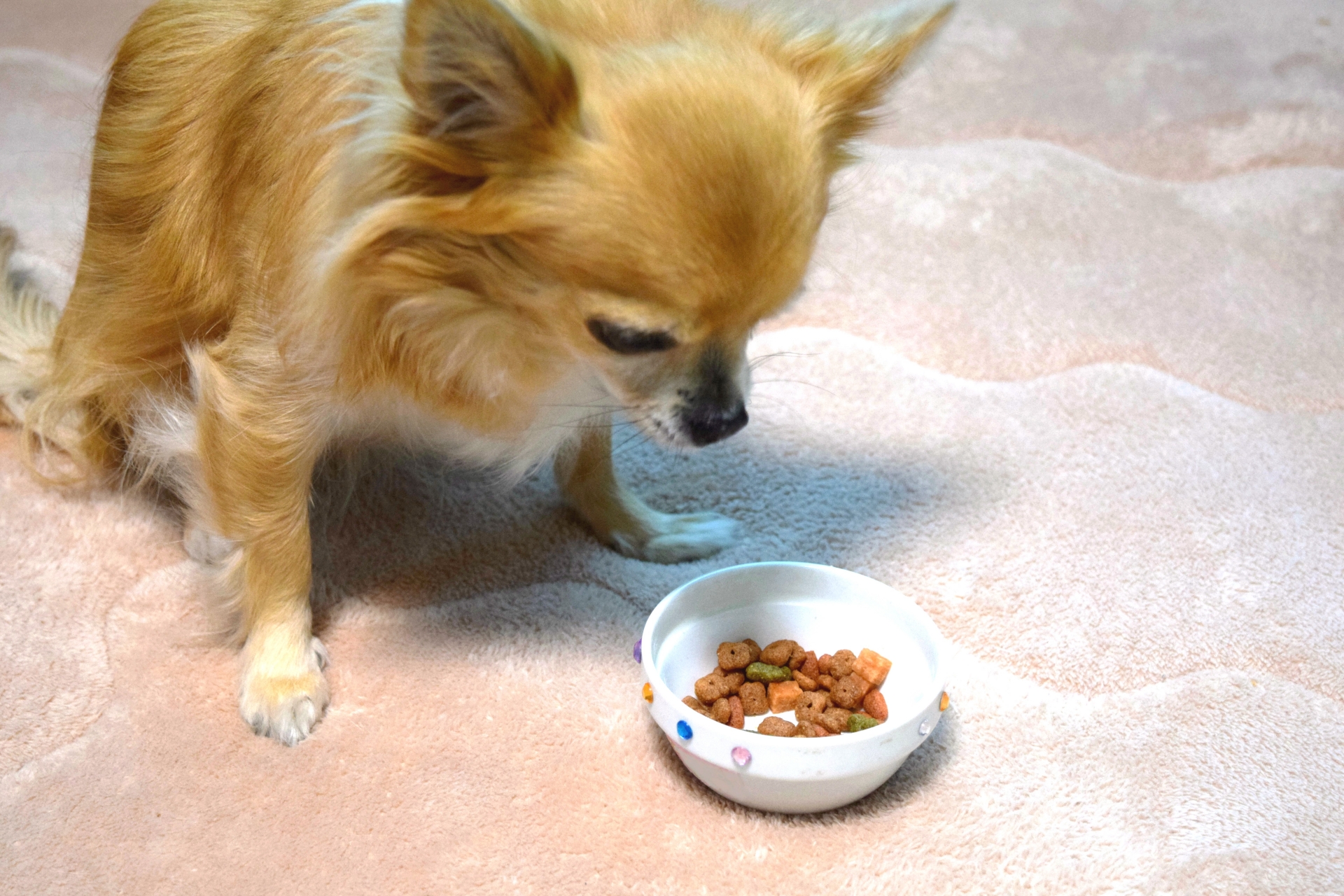
1. 食欲をチェックする
ごはんをいつも通り食べて、食後に出るあくびは、眠気からくる生理的なあくびであることが多いため、基本的には心配いりません。今まで食べていたごはんを残すようになる、食欲がなくなる、今まで大好きだったものを急に食べなくなる、などの変化がある場合はその他の症状もあわせてチェックして、心配であれば動物病院を受診しましょう。
2. 排泄物をチェックする
ウンチやオシッコの状態もチェックしましょう。1日の回数や量、色・臭いなどによって健康状態を確認することができます。普段と比べて回数や状態が極端に変わる、下痢が続く、などの症状があくびと一緒に出ているときには、動物病院を受診しましょう。
3. 口臭をチェックする
口腔(口内)環境は、腎臓、肝臓、膵臓、心臓、皮膚、骨、肥満、アレルギーなどの健康状態と密接な関係があり、口腔環境の衛生状態は「臓器への菌の転移」や「ウィルス感染」に繋がる可能性のあることが分かっています。
・「生臭い」「魚臭い」
口腔内の乾燥が考えられます。犬の口の中は通常唾液で潤っていますが、口腔内の水分が不足すると唾液がねばっこく濃縮されて口臭の原因になります。
・「腐敗臭」のような口臭
犬の口臭原因として最も多いのは、歯周病が原因の口腔内腫瘍の可能性もあります。
・「酸っぱい」臭い
胃腸の不調が隠れていることがあります。特に胃炎を患っている場合、胃酸の分泌が過多になるため、嘔吐したり胃酸がこみ上げてきたりします。それが原因で胃酸由来のすっぱい臭いが口臭として感じられます。
・アンモニア臭
腎臓や肝臓が正常に働かないことで、通常は体の外に排泄される物質が体内に溜まり、それによって口臭になることがあります。
・便の臭い
口腔内の問題やひどい便秘などが影響していることもありますが、腸閉塞や腸のねじれなどの重篤な症状を起こしているおそれがあります。
4. 歩き方をチェックする
足を引きずる、ふらつく、運動をしたがらないのは、パテラやヘルニアなど骨や関節のトラブルに起因する事が多いですが、うつ病や貧血や低血糖、てんかんなどでも同じような症状が出ることがあります。あくびと一緒にこのような症状がある場合には、注意が必要です。
その他にもふらつく、歩きたがらない場合には、中毒症状、白内障、水頭症、脳腫瘍、認知症、内耳炎、などさまざまな病気が考えられますので、いつもと違うと感じた場合には、動物病院の受診をお勧めします。
89種和漢植物と無添加原材料で作られた超ヘルシーフード
アガリクスやハナビラタケ、霊芝などの有名、人気和漢植物89種を配合した無添加のドッグフード
まとめ

言葉を話せない犬にとって、あくびは犬の気持ちや状態を伝える重要なサインです。日ごろから、あくびの回数は増えていないか、ふだんと違うあくびをしていないかなど、愛犬の様子を注意深く観察することも大切です。
病気や体調不良が疑われるあくびは放っておくと、ほかの病気を併発させてしまったり、完治が遅れたりする場合があります。命にかかわる病気の早期発見につながることもあるので、ふだんのあくびと少しでも違う様子がみられる場合は、できるだけ早く動物病院を受診してください。