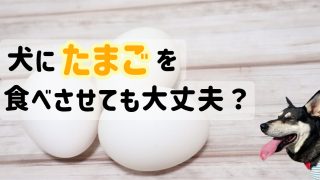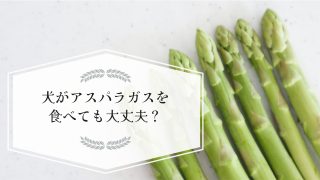Contents
犬が痙攣を起こしたら、多くの飼い主さんはビックリされるかと思います。
このページでは痙攣の原因、考えられる病気から対処法まで解説致します。
癲癇(てんかん)と痙攣の違いは?
癲癇(てんかん)と痙攣は、一般的には似た症状を引き起こす神経学的な状態であり、脳の異常活動によって引き起こされます。ただし、以下に示すように、てんかんと痙攣にはいくつかの違いがあります。
癲癇(てんかん)は、反復的な発作を特徴とする神経学的疾患であり、脳の神経細胞が異常な活動をすることによって引き起こされます。発作は、通常、短期間の脳の機能の変化と、意識障害、けいれん、筋肉のこわばり、あるいは身体的な症状などを引き起こします。てんかんは、犬や猫を含む多くの種類の動物に影響を与えます。てんかん発作が持続する場合、獣医師に相談することが必要です。
痙攣は、異常な神経刺激によって引き起こされる筋肉の反復的な収縮のことを指します。痙攣は、犬や猫を含む多くの種類の動物に影響を与えます。痙攣は、てんかんや他の神経学的問題、毒性、低血糖、低カルシウム血症、低ナトリウム血症、脳卒中、感染症、腫瘍、外傷、脳炎、糖尿病などの病気によって引き起こされることがあります。痙攣が発生した場合は、獣医師に相談することが重要です。
まとめると、癲癇(てんかん)は病気であり、脳の異常活動によって引き起こされる。痙攣は反復的な筋肉の収縮であり、様々な原因によって引き起こされる。 ということになります。
犬の痙攣が起きるメカニズム
犬の痙攣は、犬自身の意思と関係なく体の一部や全体が震え、筋肉が収縮し、ピクピクと小刻みに動いてしまう症状のことです。大脳皮質の皺(しわ)の部分に、なんらかの障害が起きると、発作が発生すると考えられています。
代表的な症状には、足をバタバタさせるようにかき回す、全身が震える、体を弓なりに反らすなどがあります。また、通常は正常な意識がないことも多いです。
犬が痙攣をする3つの原因
1. てんかん
てんかんは脳の形や大きさは正常ですが、その働きがうまくいかなくなる病気です。てんかんの判りやすい症状としては、倒れて手足が突っ張るなどの全身性の痙攣があります。てんかんの症状は、体の一部に限局されることもあります。具体的には、手足や顔面の震え、口をくちゃくちゃする、よだれが大量に出る、落ち着きがないなどの症状がみられます。てんかん発作が頻繁になる場合は、抗てんかん薬の服用によるコントロールが必要になります。
2. 筋肉疲労
運動後の筋肉の痙攣は、筋肉の疲労や電解質のバランスの乱れが原因で起こります。通常は数分以内に治まるため、過度に心配する必要はありません。また、就寝中に四肢を動かしたり、バタバタと走るような仕草をすることもありますが、これは睡眠中の筋肉の正常な動きであり、問題ありません。
3. 中毒物質の誤飲・誤食
犬が体にとって有害な物質を摂取することで引き起こされる症状を「中毒」といいます。中毒によって、神経症状の一部として痙攣などが現れることがあります。
中毒症状には痙攣の他に衰弱、よだれ、嘔吐、下痢、震えなどさまざまな症状が出ることがあり、時間経過とともに症状が悪化するため、誤食による痙攣の可能性がある場合は、ただちに病院を受診する必要があります。
〈犬に中毒を起こす可能性のある物質〉
・チョコレート
・マカデミアナッツ
・キシリトール
・カフェイン
・ニコチン
・消炎鎮痛薬(人間用の痛み止めや解熱剤など)
・殺虫剤
これらのように、犬にとって数多くの危険な食べ物があります。
犬の痙攣で考えられる病気
脳炎(髄膜脳炎)
脳の炎症を「脳炎」といいます。また、脳炎が髄膜にまで広がった状態を「髄膜脳炎」といいます。脳炎を発症すると、痙攣や震え、視覚障害などの神経症状を引き起こす原因になります。脳炎は、感染性と非感染性に分けられます。
感染性の脳炎は、ウイルス、細菌、寄生虫などの病原体が原因となり、代表的な病気には、犬ジステンパー脳炎、狂犬病、細菌性髄膜炎、クリプトコッカス症、ネオスポラ症などがあります。
非感染性は、自己免疫反応や遺伝子の異常、特定の物質に対する過敏反応などが原因となり、壊死性髄膜脳炎、壊死性白質脳炎、肉芽腫成髄膜脳炎、突発性振戦症候群などがあります。
<脳炎の症状>
・元気がない
・食欲がない
・歩き方がおかしい
・ふらつく
・うまく動けない
・起き上がれない
・旋回運動:意味もなく一定の方向にグルグルと回り続ける
・視覚障害
・痙攣
・意識障害 ・・・など
※炎症が起こっている部位や広がりによっては、重篤な症状を引き起こす場合もあります。
脳腫瘍
脳腫瘍とは、頭蓋骨の中に発生する腫瘍の総称です。発生源によって「原発性脳腫瘍」と「転移性脳腫瘍」に分けられます。
原発性脳腫瘍は、脳や脳を包む膜、脳神経などの組織から発生します。種類は150種類以上あり、発生部位や細胞の種類によって悪性度や治療法が異なります。
転移性脳腫瘍は、他の臓器の腫瘍が脳に転移して発生します。肺がんや乳がん、腎がんなどの転移が多いとされています。
腫瘍は脳を圧迫し、さまざまな神経症状を引き起こします。頭痛や吐き気、嘔吐、めまい、視力障害、運動障害、言語障害など、症状は腫瘍の位置や大きさによって異なります。
<脳腫瘍の症状>
・痙攣
・頸部知覚過敏
・旋回運動:意味もなく一定の方向にグルグルと回り続ける
・運動失調:体の平衡や姿勢 が保てない
・捻転斜頸:首がねじれた状態になって姿勢をうまく制御できなくなる
など、腫瘍がある部位により、さまざまな神経症状が見られます。
水頭症
水頭症は、脳室と呼ばれる空洞に過剰な脳脊髄液がたまることで、脳の圧迫による障害や、萎縮を起こす病気です。さまざまな神経症状が生じ、障害が出ている脳の部位に関連して下記のような症状が現れます。
<水頭症の症状>
・落ち着きがない
・異常行動
・旋回運動:意味もなく一定の方向にグルグルと回り続ける
・歩行困難
・痙攣
・視覚障害
・意識障害
犬の痙攣への対処法
周りの物を避け、そっと声をかけ見守ってあげる
- 頭部をクッションや毛布で保護をする
犬の周囲に、危険な物や衝突しそうな物がないか確認してください。痙攣時に動きが荒くなる犬もいますので、周りに何かあればそれを移動させて安全を確保しましょう。犬を力ずくで抑えつけたり、激しく揺さぶったり、大声で名前を呼ぶのは絶対に避けてください。静かに話しかけることで、犬が落ち着くことがあるようです。
- 噛まれないよう注意する
痙攣中の犬に寄り添いたくなる気持ちは理解できますが、顔の周りを触ってはいけません。誤って噛む時は無意識なので、噛む力も非常に強力で危険です。
- 周囲を涼しく保つ
筋肉が発する熱で、体温が異常に上昇することがあるため、涼しい環境を整えてあげましょう。それでも、明らかに体温の異常な上昇(体温40℃以上)がある場合は、体に水をかけ、風をあてて体温を下げてあげましょう。
- 動画を撮影する
ほとんどの痙攣は2〜3分で、最長でも5分程度で終息します。痙攣中の様子や持続時間を正確に伝えられるように、動画に撮ったりしておきましょう。痙攣にはさまざまな症状があるため、動画があると動物病院で説明しやすいです。また、痙攣が収まった後の状態(もうろうとしたり、目が回ったりすることなど)も動画に記録し、けいれん後の様子を観察することを忘れずに行ってください。
- 誤食の痕跡がないか確認する
誤食による「中毒」で痙攣することがあるため、周囲を確認しましょう。
用意が整い次第、すぐに病院で診てもらう
痙攣は生命に関わる緊急性が高い症状の1つです。決して自宅で様子をみるのではなく、直ぐに動物病院に連れて行く準備をしましょう。犬のけいれんは夜によく発生するので、夜間対応可能な動物病院を予め探しておくと、緊急の際にも安心です。
痙攣が起こっている間とその後の様子をビデオに収めておくことが望ましいです。痙攣の具体的な症状は、言葉だけでは伝えにくいものがあります。ビデオがあれば、その状態がすぐに理解でき、治療を進める際の助けとなります。また、痙攣が発生する前に、いつもと異なることをしていなかったかなどのメモも持っていると、診察がスムーズに進みます。
犬の痙攣を未然に防ぐ方法
異物を誤飲しないように、細心の注意を払う
犬が飲み込む可能性のあるものを、室内に置かないようにしましょう。特に中毒を起こす可能性のある人間用の薬や食品などはしっかり管理しましょう。犬の誤飲や誤食は、屋内でも屋外でも発生する可能性がありますが、飼い主の注意によって予防できます。
事故数の多い異物の誤飲は、非常に危険な事態を招く恐れがありますので細心の注意を払いましょう。
定期的に健康診断を受診する
定期的な健康診断を受けることにより、痙攣を引き起こす可能性のある疾患を早期に見つけ出せます。現在健康であっても、将来の健康を守るためには健康診断を定期的に行うことが重要です。
てんかん予防のための食事や栄養素
定期的な健康診断を受けることにより、痙攣を引き起こす可能性のある疾患を早期に見つけ出せます。現在健康であっても、将来の健康を守るためには健康診断を定期的に行うことが重要です。
◆アミノ酸(BCAA)
神経伝達物質を作るためには、アミノ酸を素に、ビタミンB群(ナイアシン、ビタミンB6)やマグネシウム等のミネラルが必要です。とくに、必須アミノ酸(BCAA)は体内で合成されないため、意識的に摂取することが必要となります。
◆オメガ3脂肪酸
脳神経に豊富に含まれる成分ですが、体内で合成することができず不足しがちです。炎症を防ぐ役割があり、痙攣発作の予防につながります。青魚やアマニ油、エゴマ油などに含まれています。
◆中鎖脂肪酸(MCT)
肝臓で代謝され、ケトン体となる中鎖脂肪酸は、ブドウ糖の代わりに脳のエネルギー源となります。
◆抗酸化物質
脳神経の酸化を防ぐ役割があり、痙攣発作の予防につながります。 ビタミンC、ビタミンEなどのビタミン類や、ポリフェノール、カテキンなどのファイトケミカルが挙げられます。
これらの栄養素は脳に良いとされていますが、それぞれ過剰に摂取したり、摂取の仕方によっては、デメリットが生じるものもあります。
例えばアミノ酸を摂取するために、お肉のみを摂りすぎると腎臓、肝臓などの内臓へ負担がかかります。また、抗酸化物質は過剰に摂取することで、尿pHがアルカリ性に傾く原因のひとつとなります。そのため、上記の栄養素を含んだ、バランスの良いフードを選ぶことが重要です。
てんかん予防におすすめの「脳に良い」ドッグフードとサプリメント
脳に良いヤマブシタケ、免疫力の活性化としてアガリクスや霊芝なども配合のドッグフードとサプリで、てんかんケア
まとめ
犬の痙攣にはさまざまな原因が考えられ、治療法も原因に応じて異なります。大切なのは、犬が痙攣を起こした時に飼い主さんがパニックを起こさないことです。落ち着いて発作時間を計ったり、できれば動画を撮影したりしておきましょう。
また、痙攣が起きたときに駆け込める病院を日頃からリストアップしておくとよいでしょう。普段通っている病院だけでなく、もっと家に近い病院や、深夜や早朝の時間帯に対応可能な病院もリストに加えておけると安心でしょう。

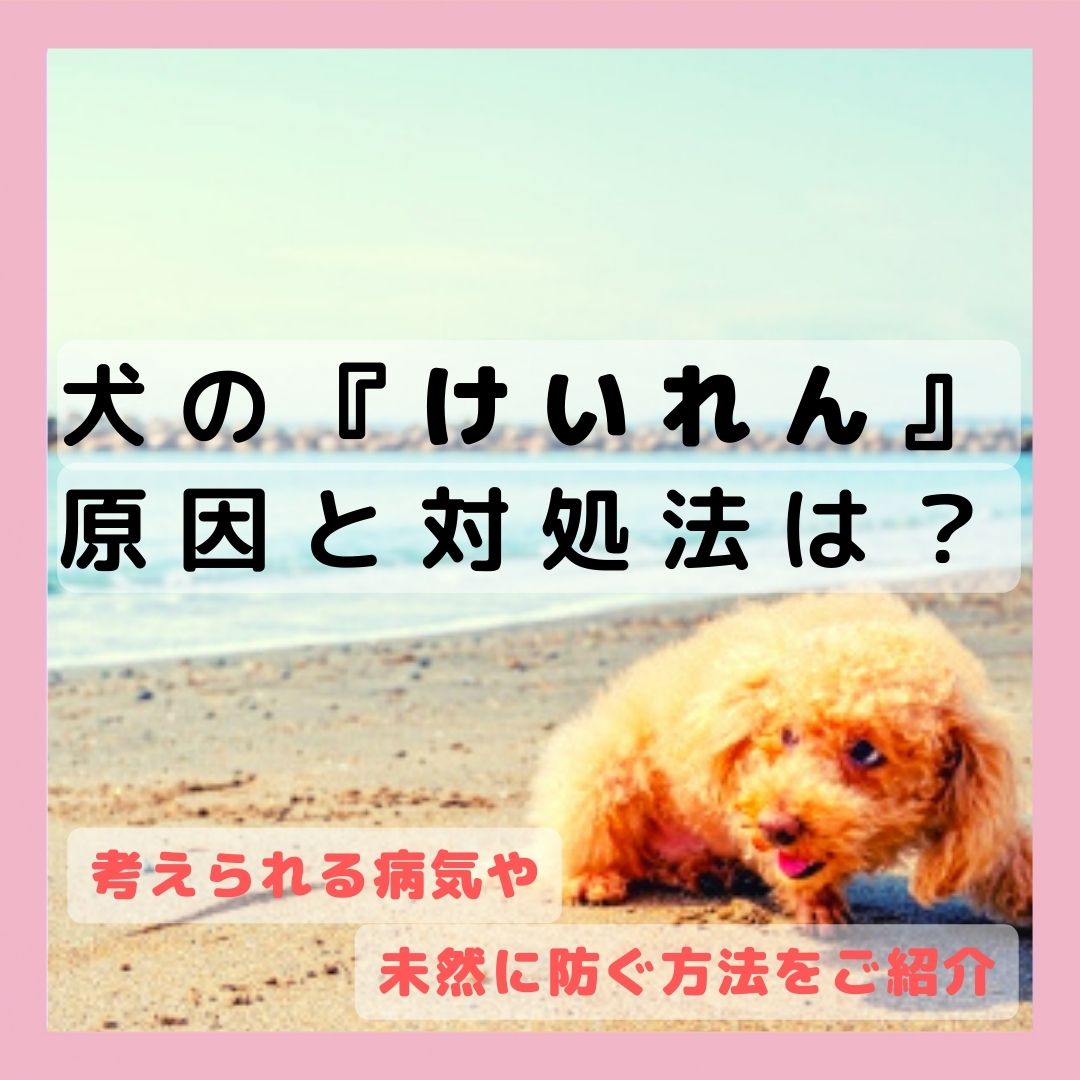
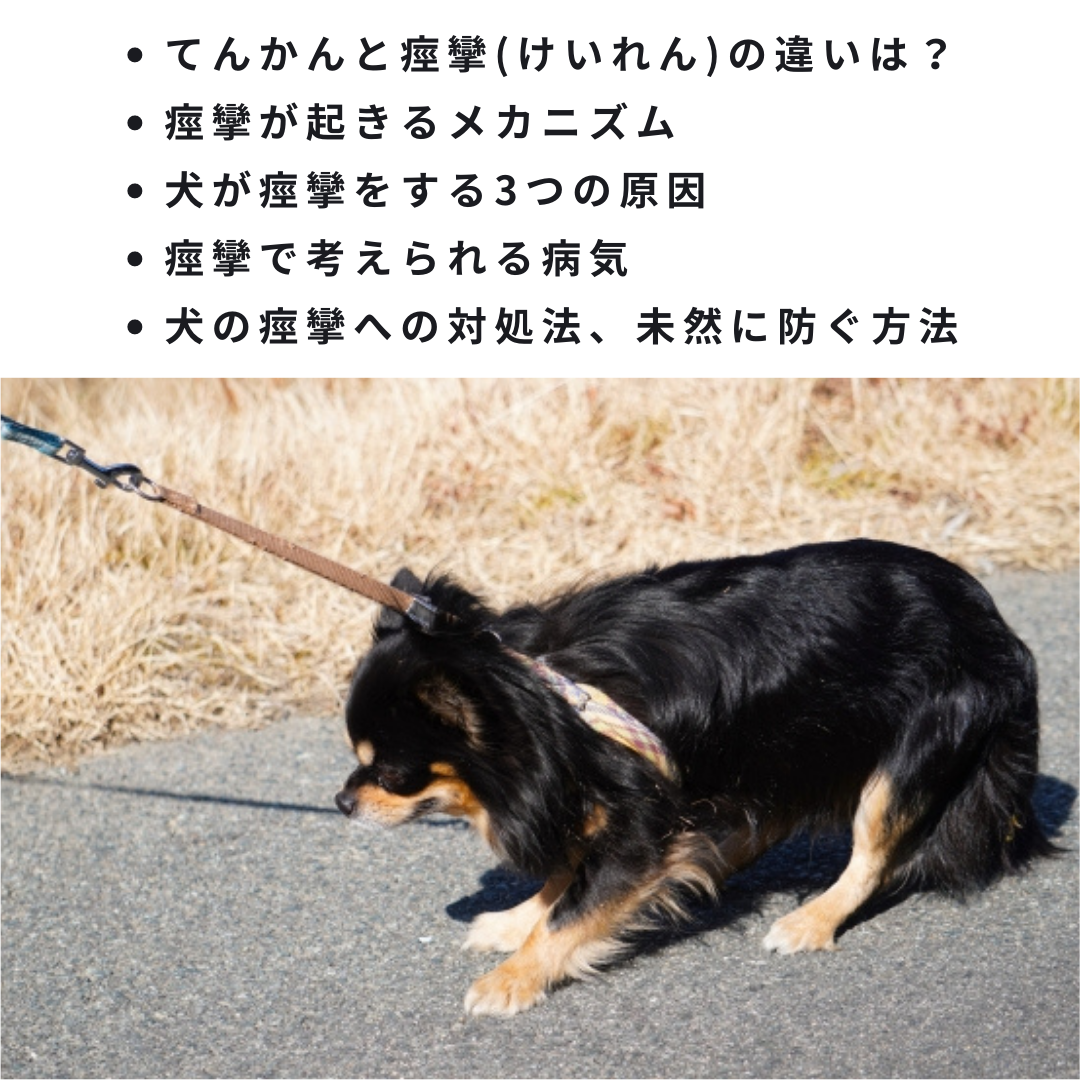
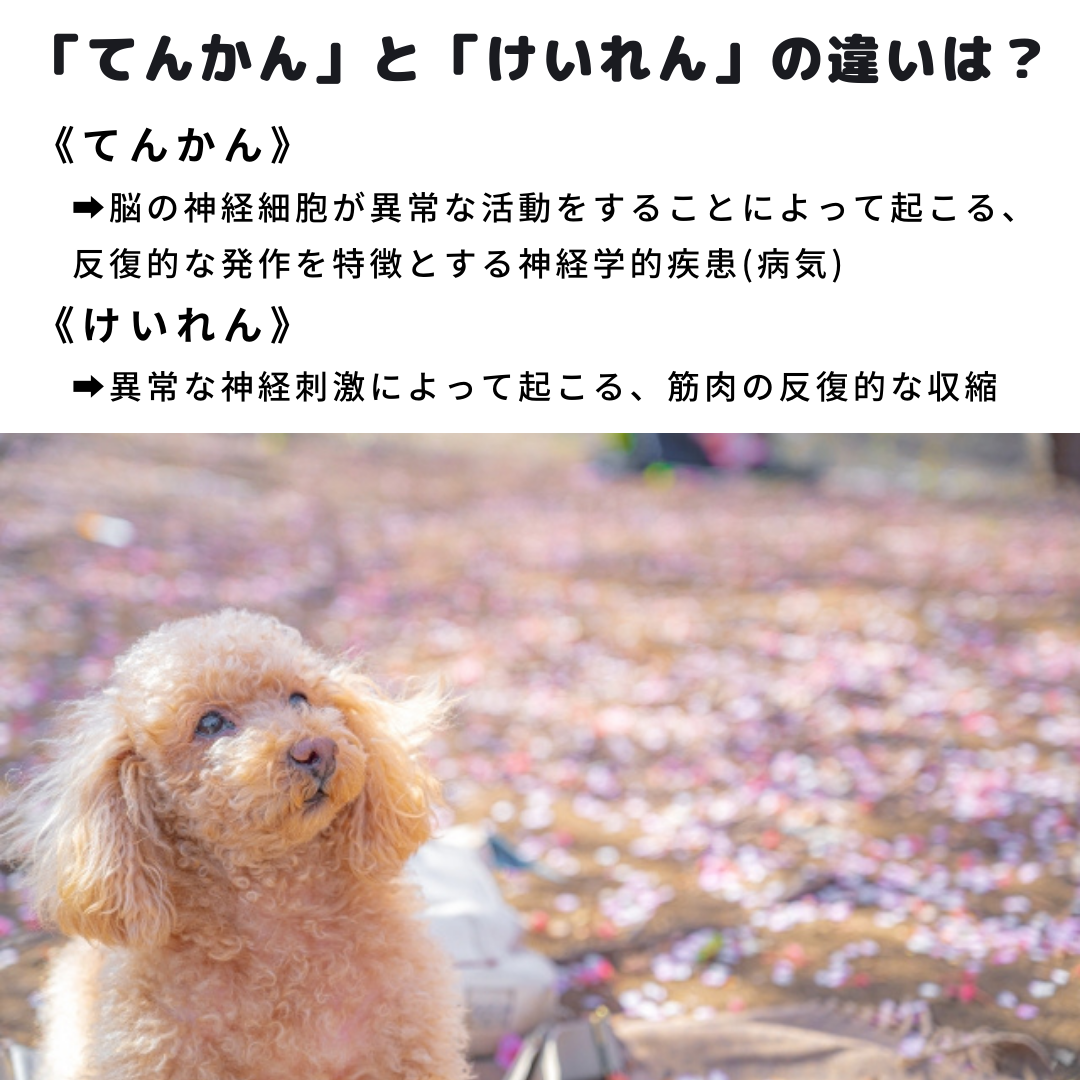
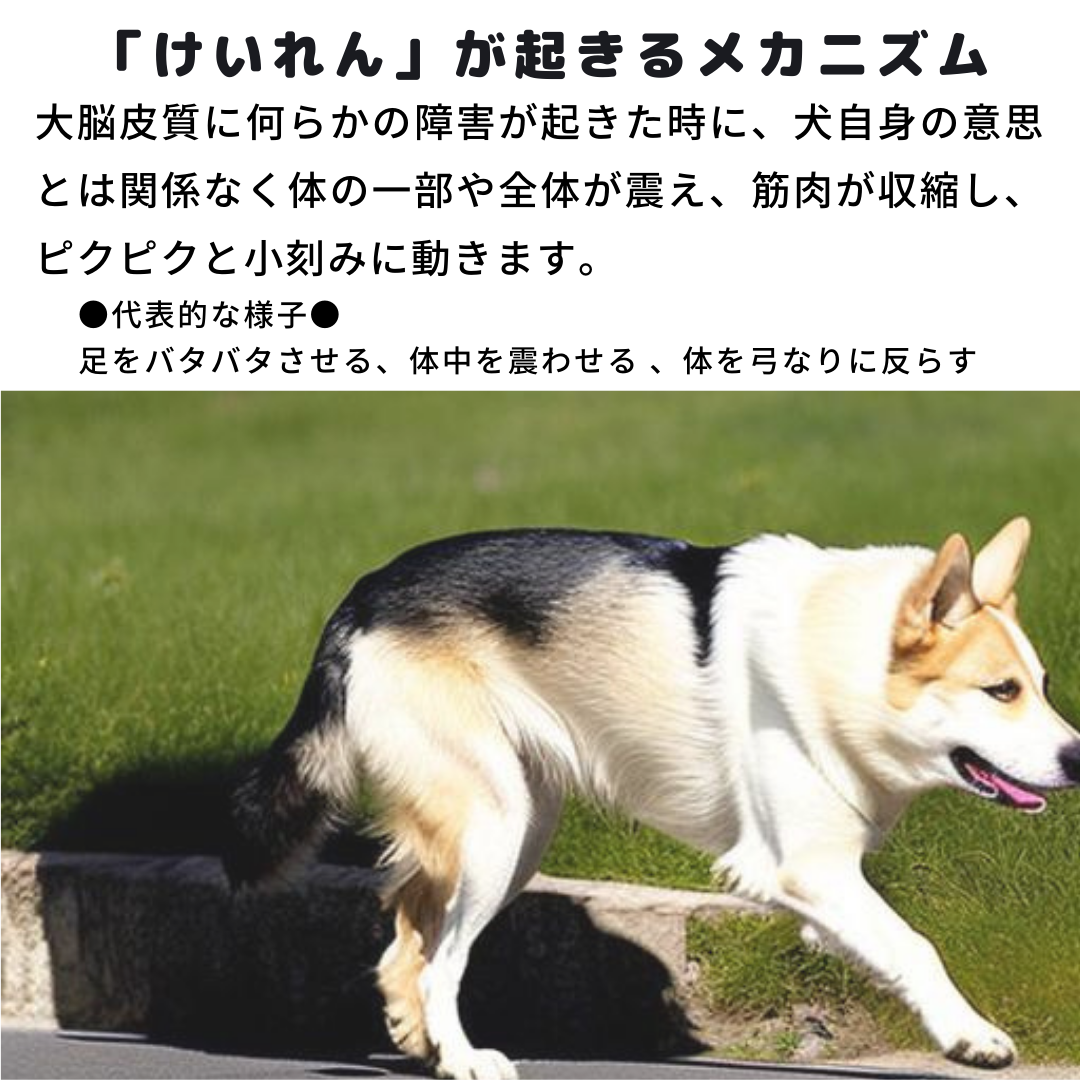
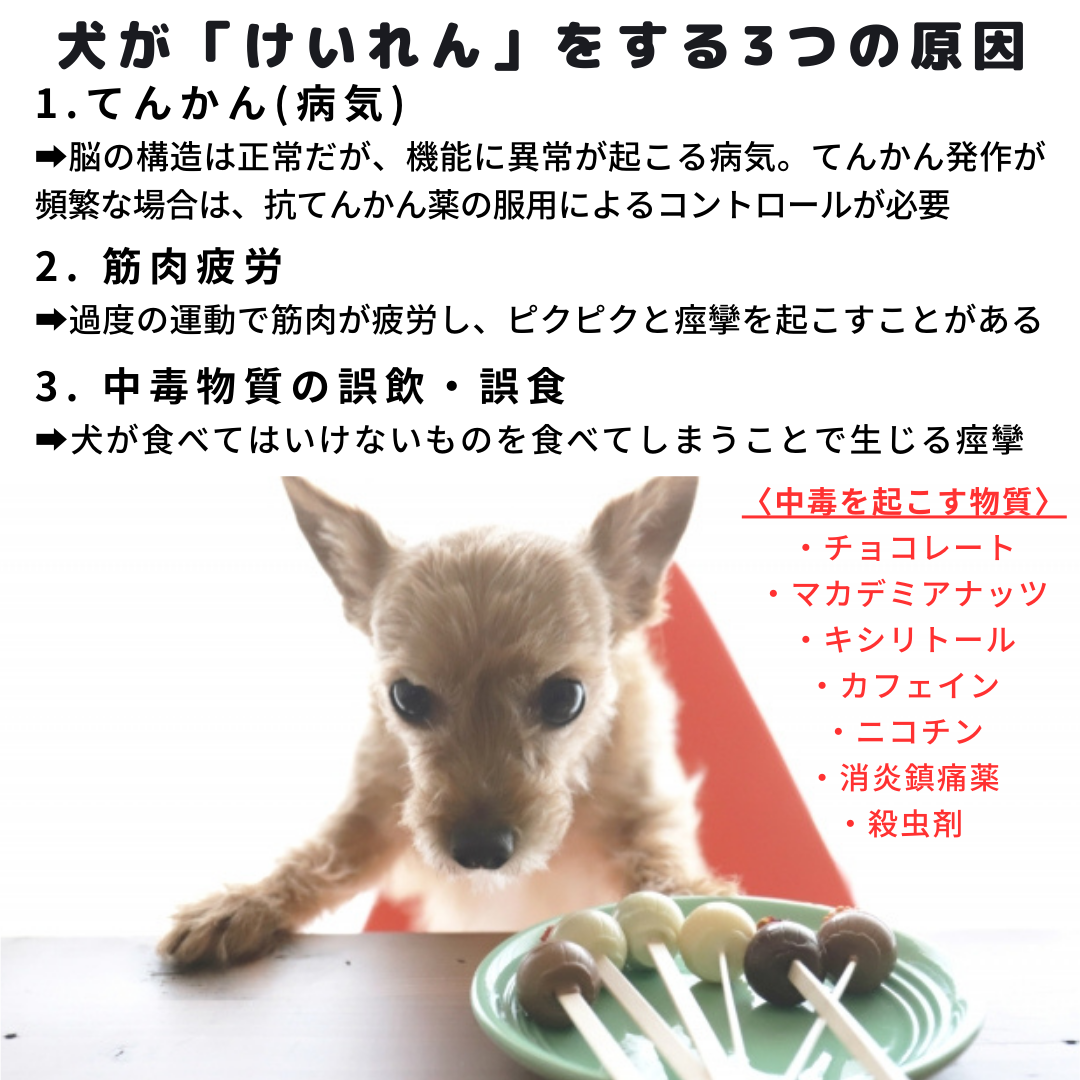
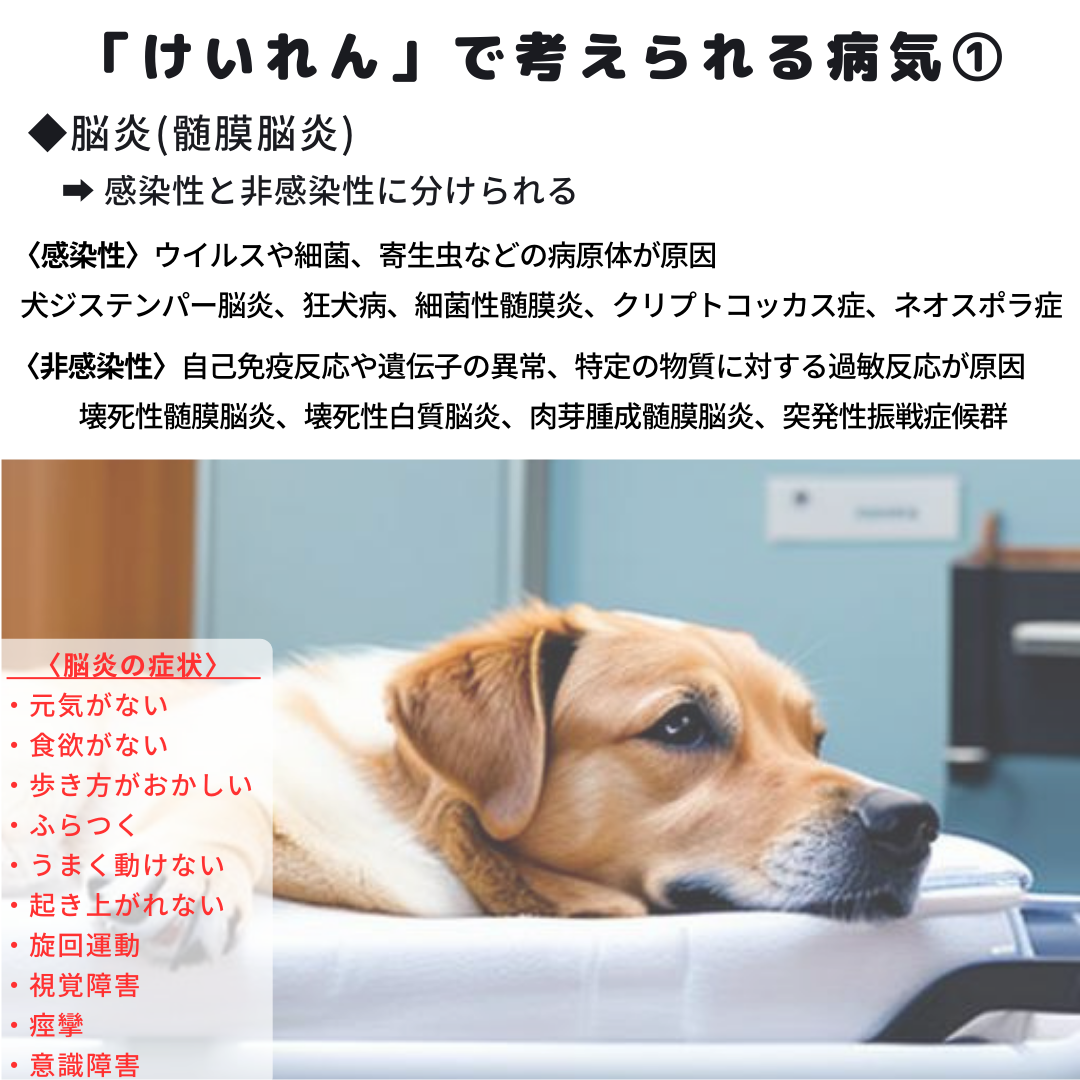

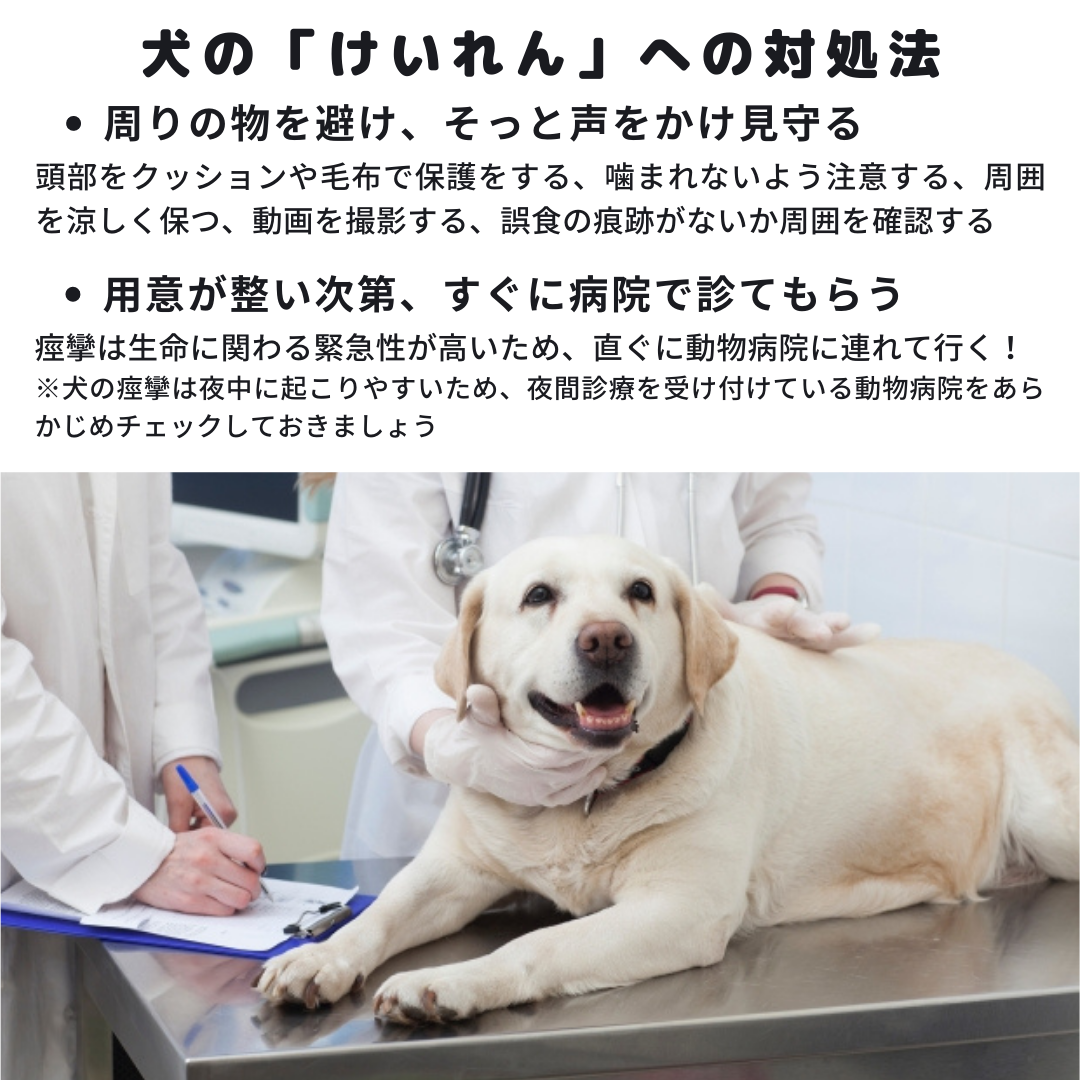
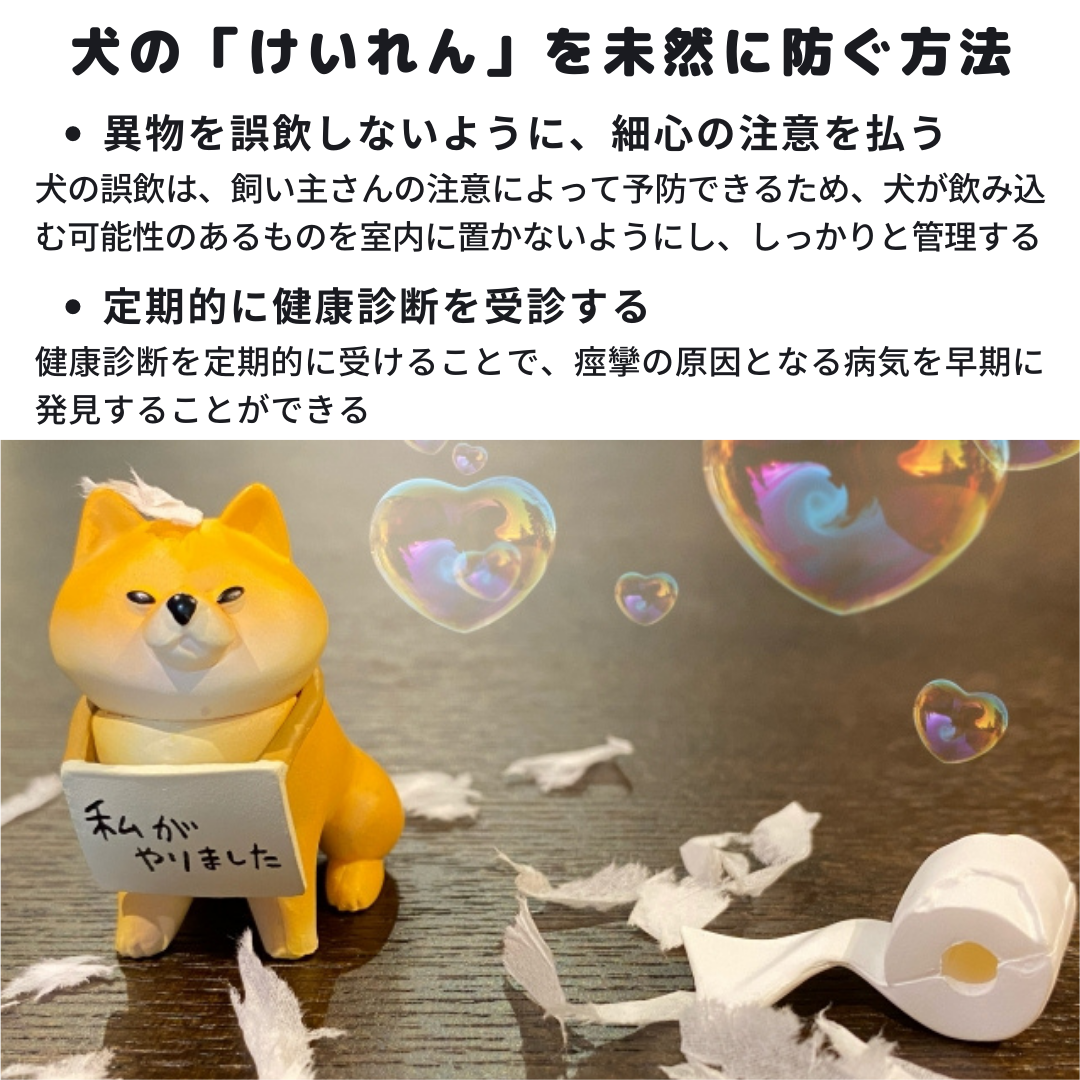
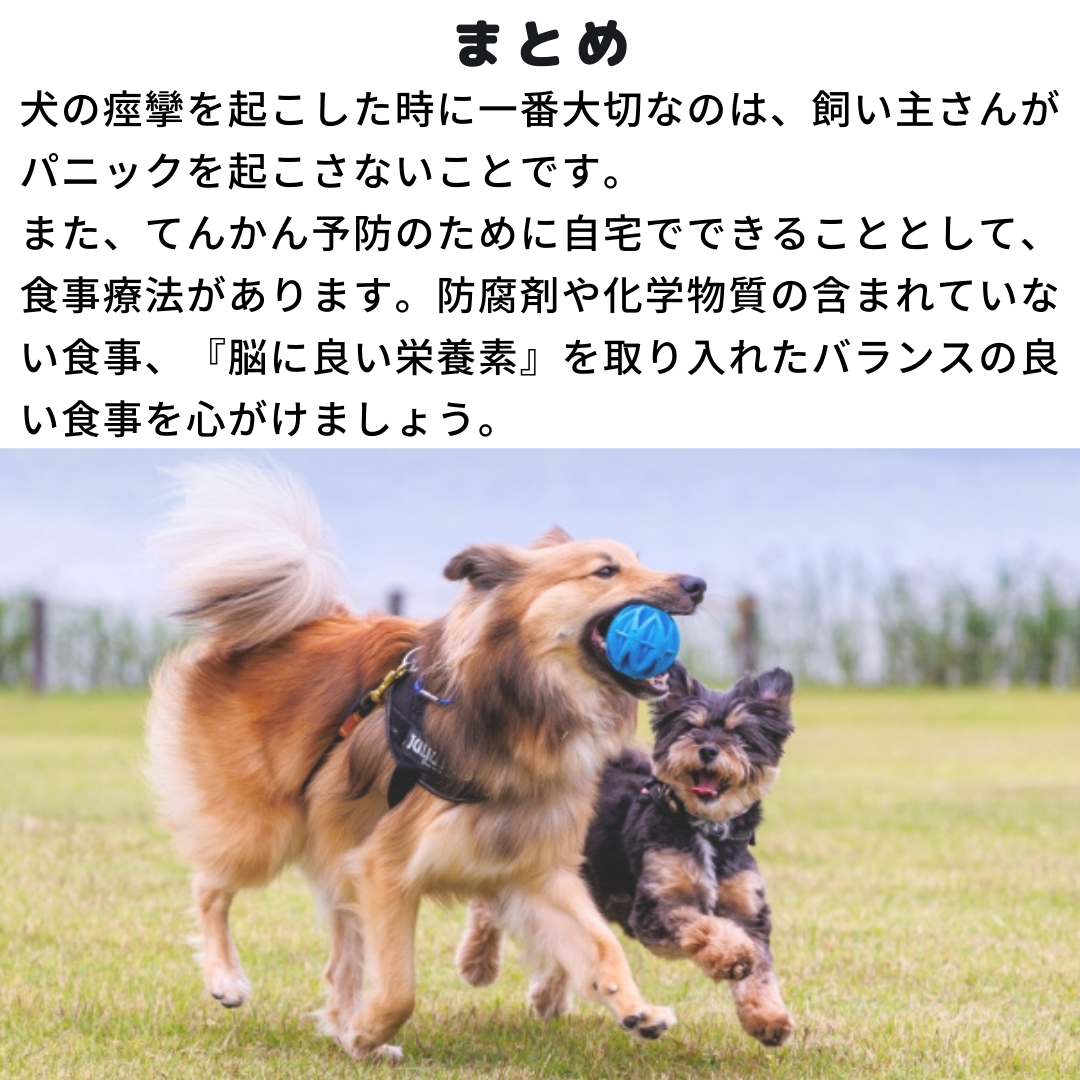










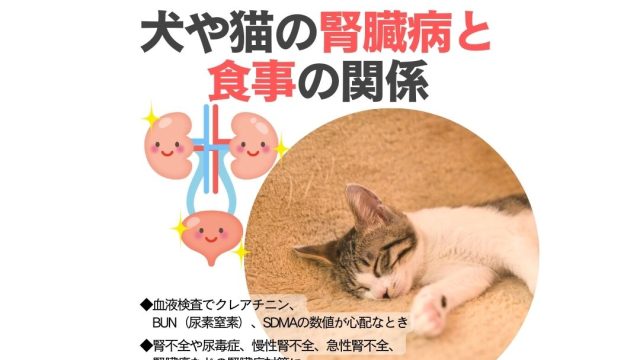







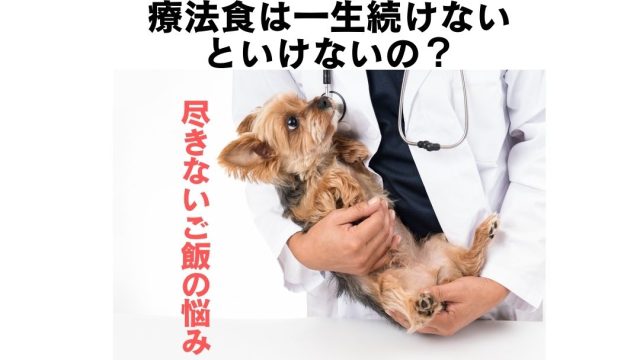







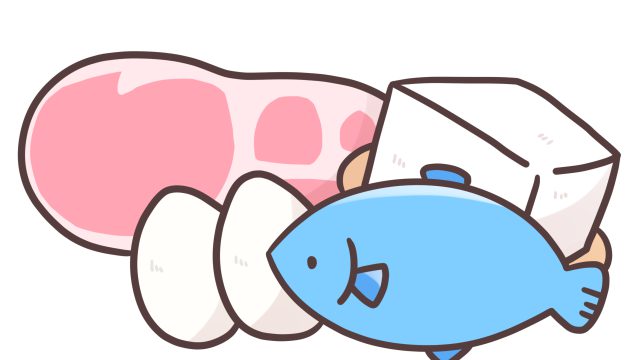



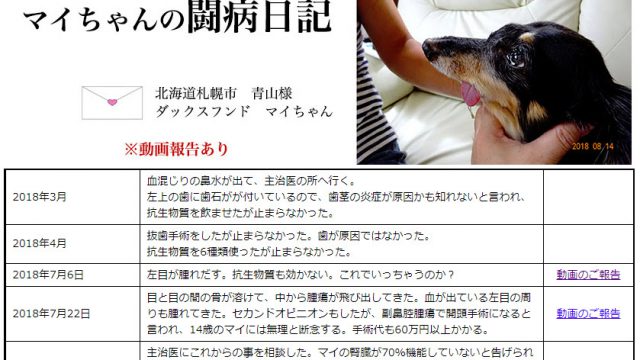
-640x360.jpg)