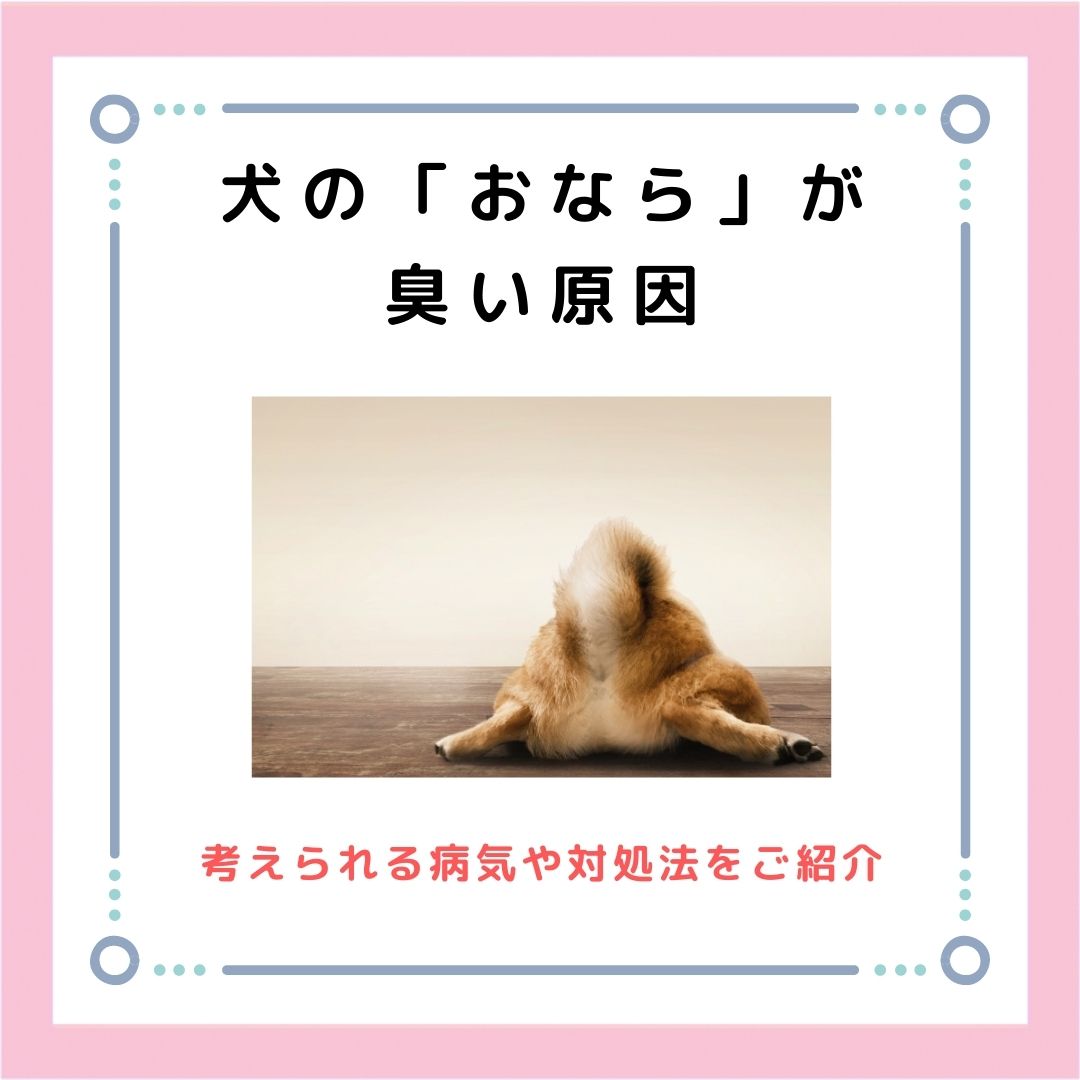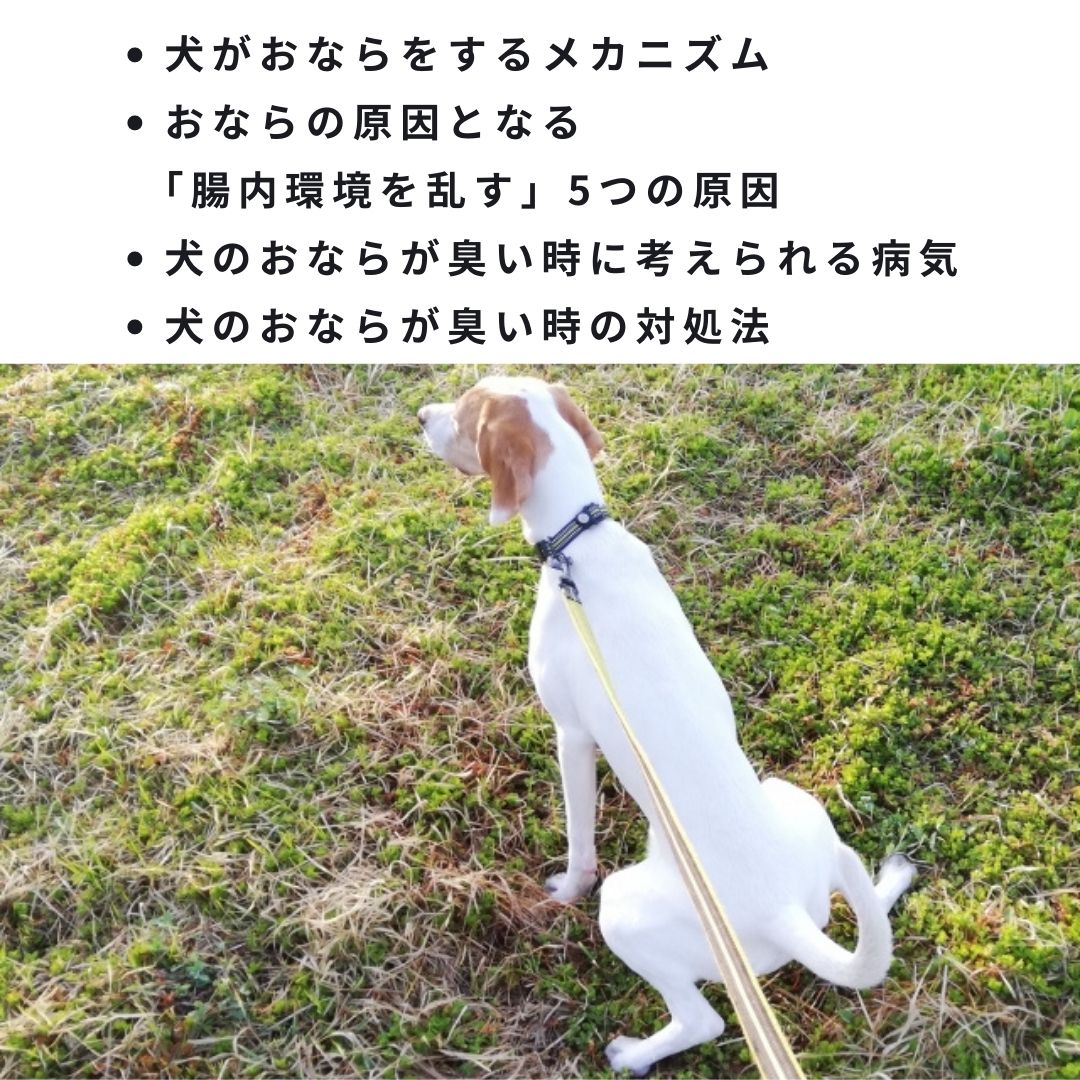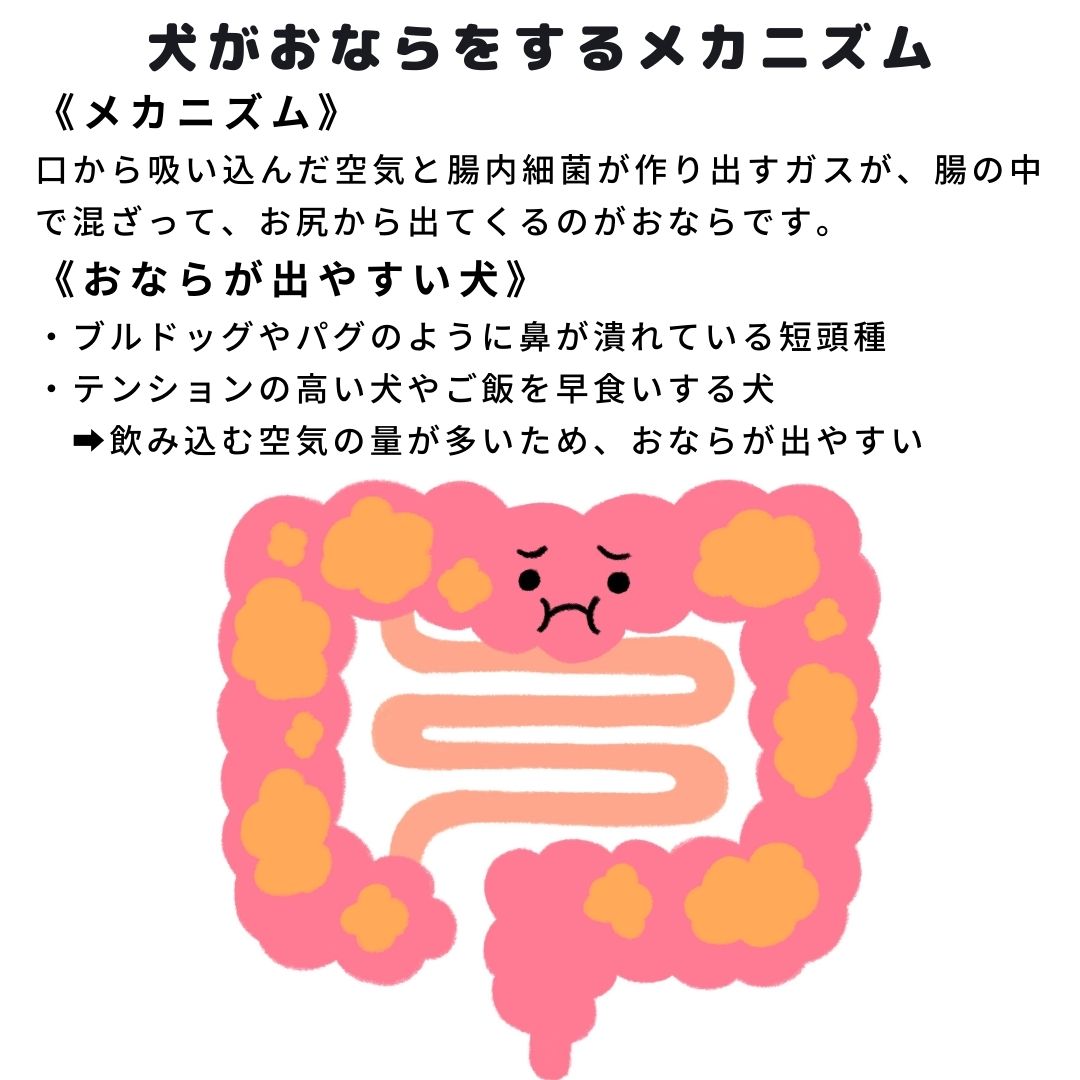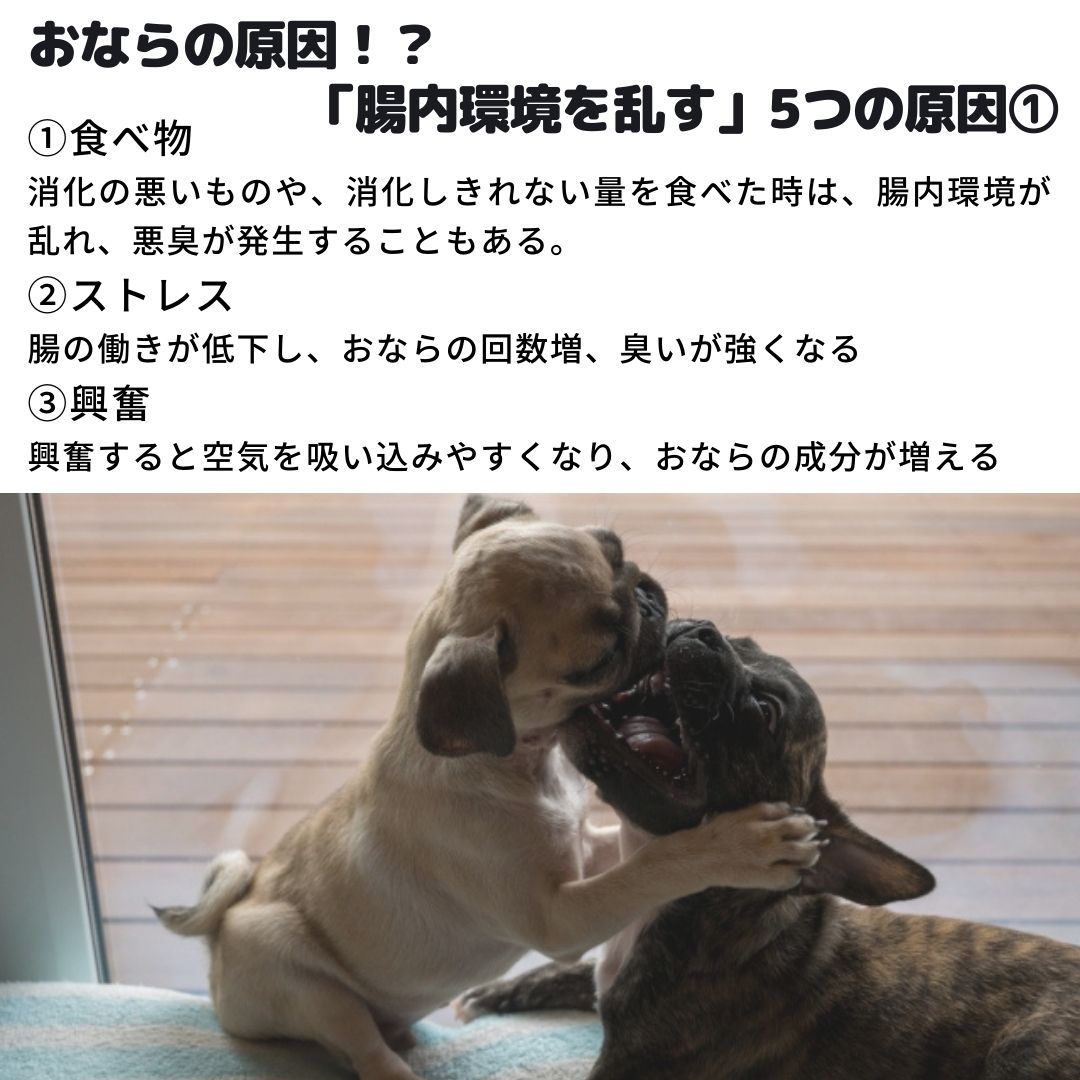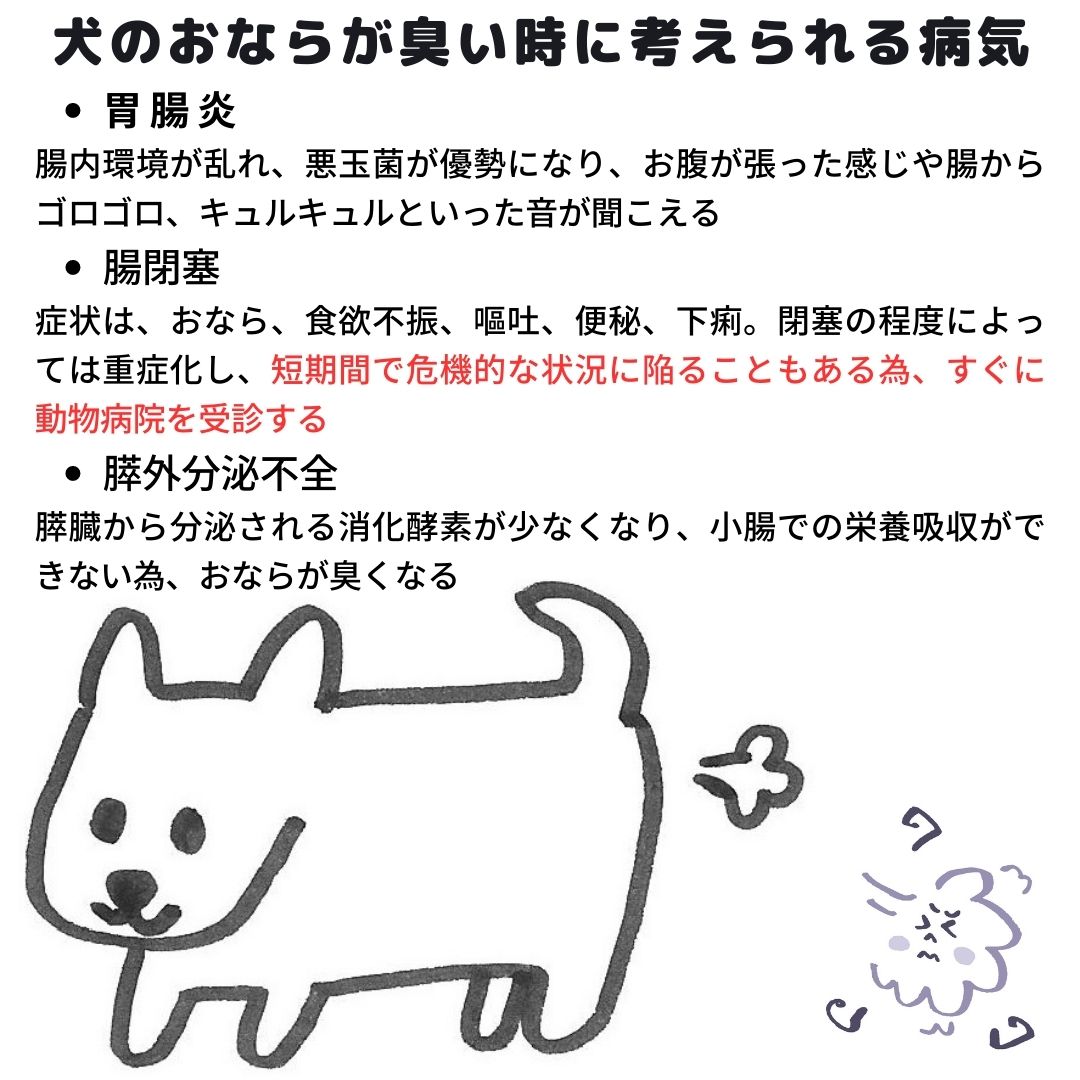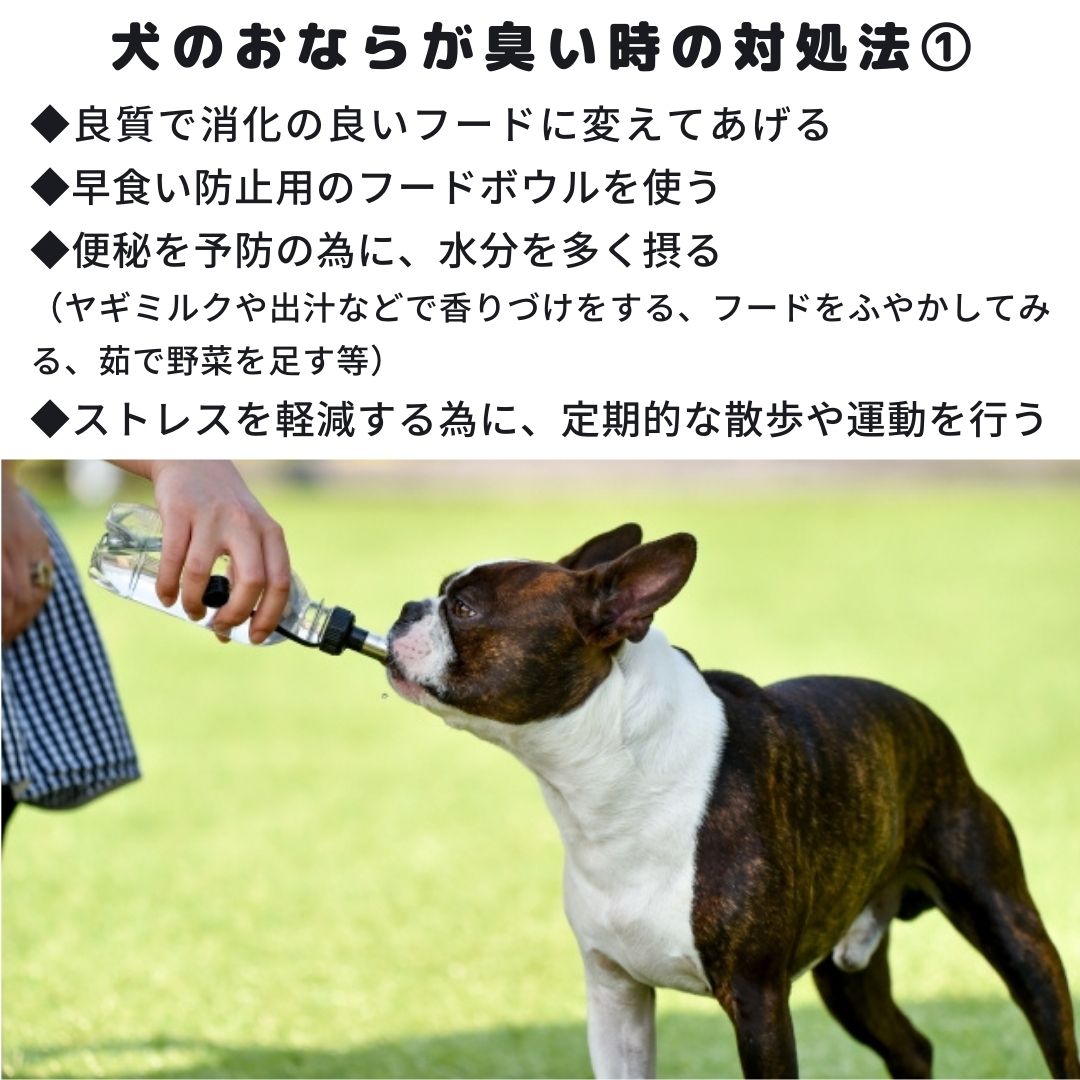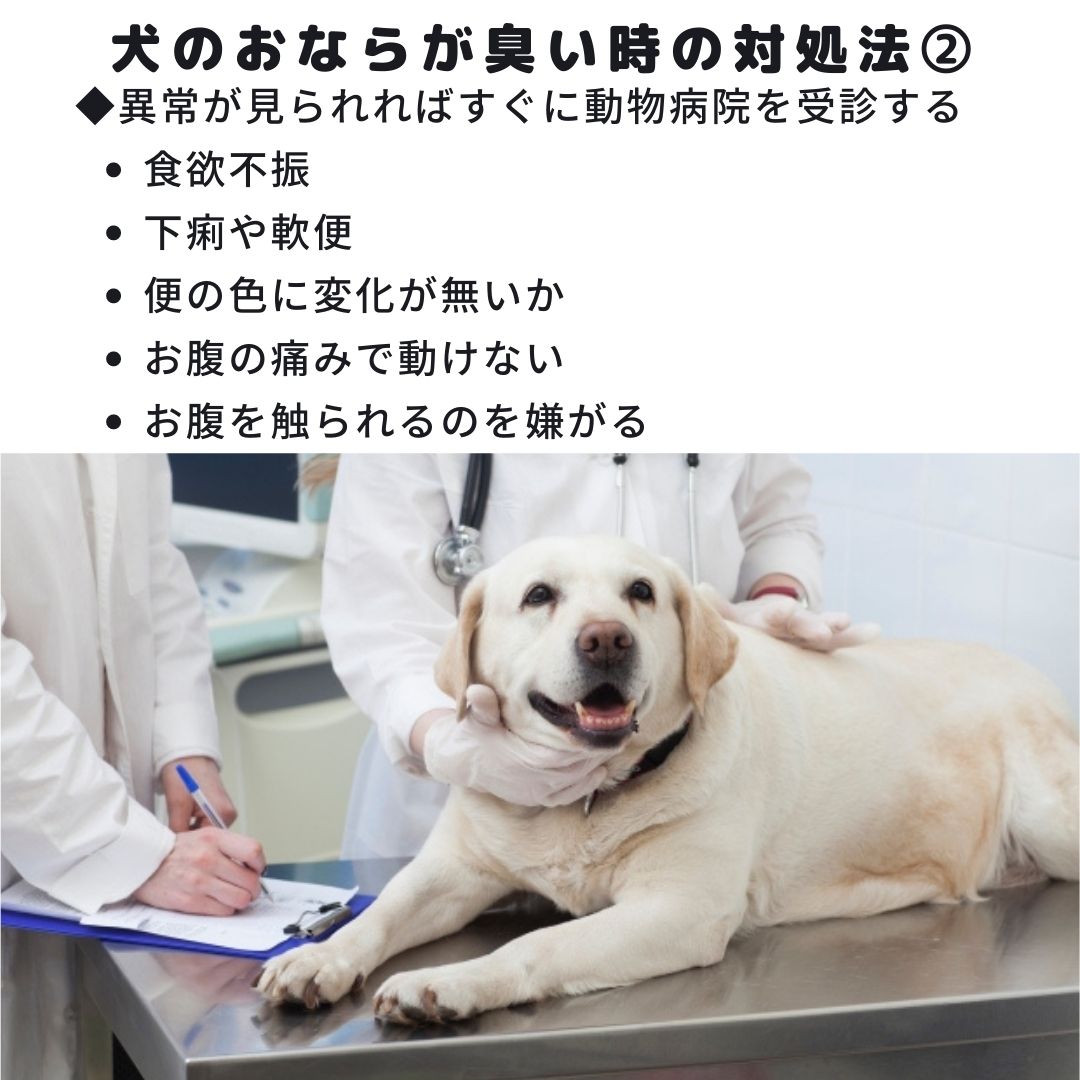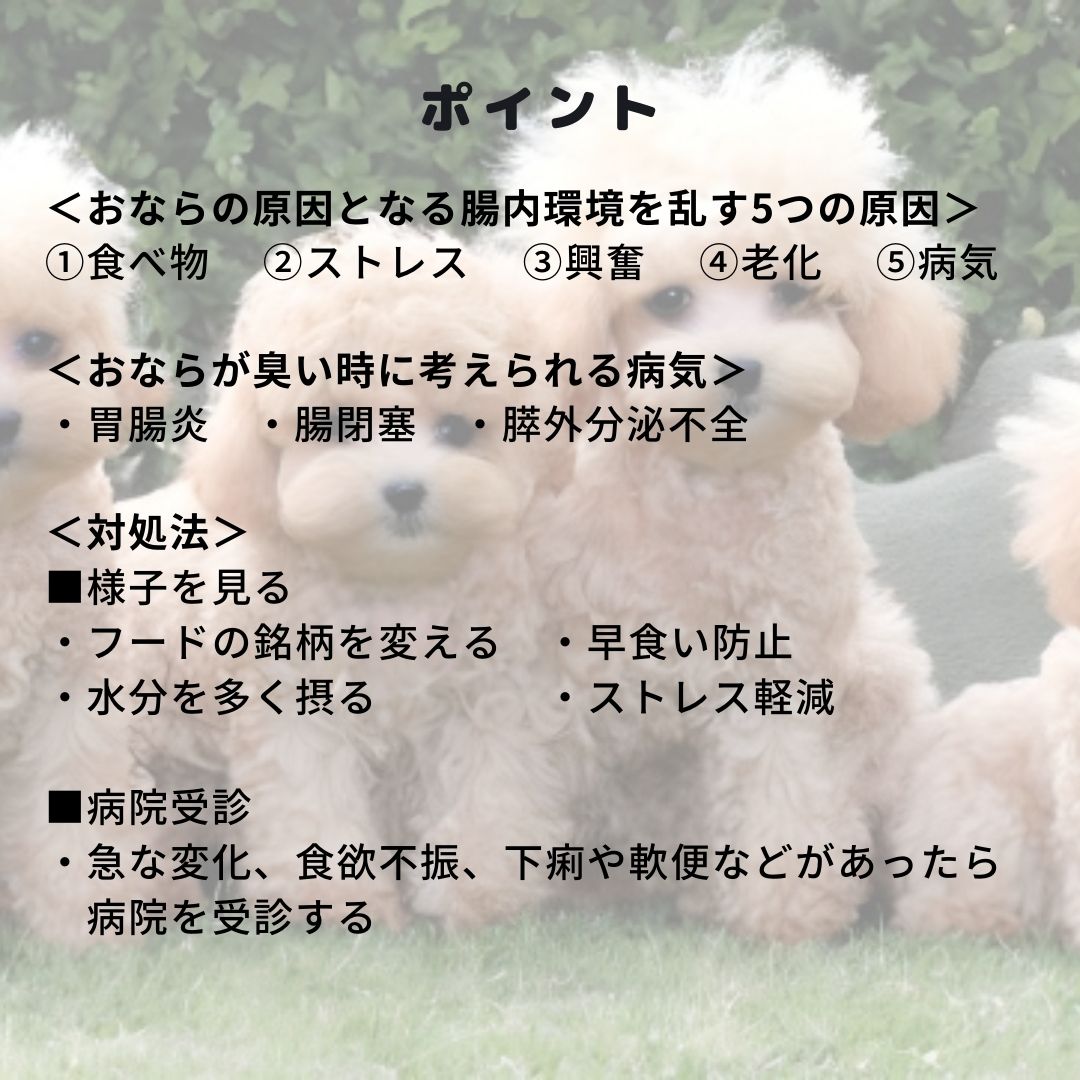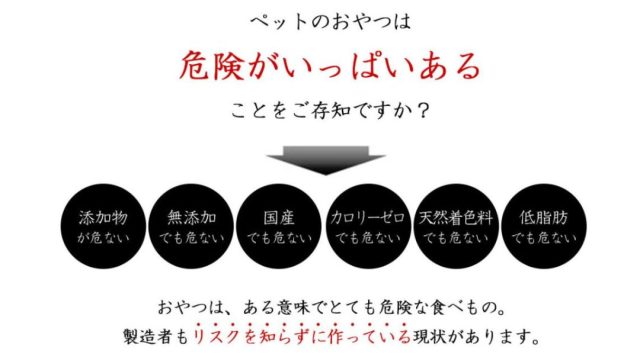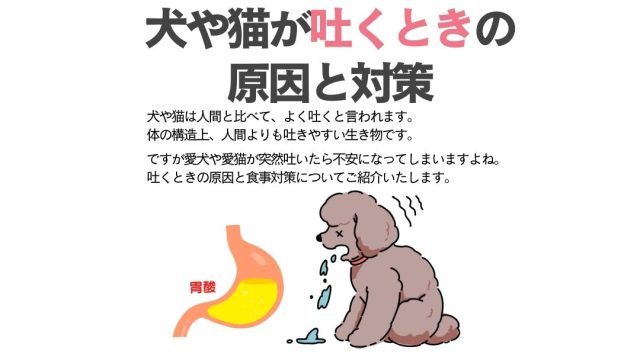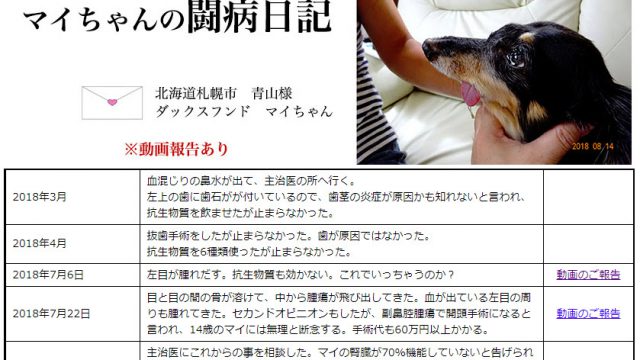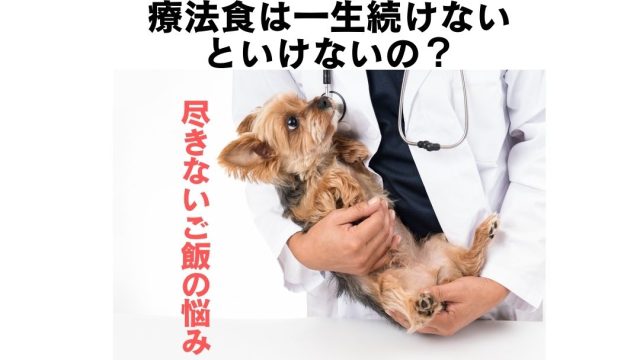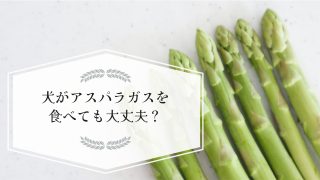Contents
犬でも人間と同様におならをします。おならは体の中を反映したサインのひとつ。
おならが臭い場合、どんな原因や病気が考えられるのか、また、その対処法を解説します。
犬がおならをするメカニズム
犬も人間と同様におならをすることがあります。おならは、腸にたまったガスが肛門から排出される現象ですが、そのガスの成分のほとんどは通常、口から吸い込んだ空気です。
通常、犬が呼吸で吸い込んだ空気は肺に送られますが、胃に入った空気のうち、げっぷとして排出されないものは、そのまま腸を通って排出されます。そして、空気以外の成分は、食物が腸内細菌によって分解される際に発生するガスです。これらのガス成分が腸内で混ざり合い、最終的におならになります。
ブルドッグやパグなど、鼻が潰れている短頭種の犬は、通常よりも呼吸が苦しいことがあり、それに伴って取り込む空気の量も増えることがあります。このため、短頭種犬は一般的に、ガスがたまりやすい犬種として広く知られています。
さらに、短頭種でない場合でも、興奮しやすい犬や食事を急いで食べる犬なども、通常よりも多くの空気を取り込むことがあります。結果として、通常よりおならが出やすくなるのです。
犬がおならをする主な原因
犬がおならをする主な原因は以下の5つです。
- 食べ物
- ストレス
- 興奮
- 老化
- 病気
それぞれの原因について、以下で詳しく解説していきます。
1. 食べ物
基本的に、犬が食事を摂ると、おならが発生する可能性があります。特に食物繊維が多く含まれる食品を摂ると、腸内細菌の活動が活性化され、ガスが発生しやすくなることから、おならが出やすくなるケースがあります。
消化が遅い食べ物や大量に摂取した消化しきれない食事は、腸内に長時間滞留しやすく、異常な発酵が起こる可能性があります。この場合、腸内環境が乱れ、悪臭が発生することもあります。
2. ストレス
犬がストレスを抱えると、おならをしやすくなります。
犬がストレスを感じると、腸の機能が低下し、腸内環境のバランスが崩れる場合があります。その結果、おならの頻度や回数が増え、臭いが強くなることがあります。
3. 興奮
犬のおならは、「興奮しやすい」ことが原因の可能性もあります。
犬が興奮している際は、空気を積極的に吸い込みやすくなると考えられます。興奮しているために急いでご飯を食べる犬は、通常よりも多くの空気を一緒に飲み込んでしまうことがあります。これによって、おならの原因となる成分が増え、おならの発生回数も増加する可能性が考えられます。
4. 老化
老化も犬がおならをする原因の1つです。犬も加齢によって、腸の消化吸収能力がだんだんと弱くなります。
このような場合、同じ食品でも消化と吸収が難しくなり、それが結果として腸内細菌によるガスの生成量の増加と、おならの頻度の増加につながることがあるかもしれません。
5. 病気
消化器の疾患や食物アレルギーによって腸内環境が悪化すると、おならが出やすくなるケースがあります。しかし、これ以外にも、肺炎や気管支炎などの呼吸器系の疾患、心臓病などの循環器系の疾患、膵炎や関節炎といった体の他の部分に痛みを引き起こす疾患でも、おならが出やすくなるケースがあります。
これらの病気では、呼吸が苦しくなったり、または痛みを伴うことが一般的であり、これに伴って通常よりも呼吸回数が増加し、空気の取り込み量が増えることがあります。このため、おならの発生頻度が高くなることがあるのです。
犬のおならが臭い時に考えられる病気
犬のおならが臭い時には、以下の病気を患っている可能性もあります。
- 胃腸炎
- 腸閉塞
- 膵外分泌不全
それぞれの病気について、詳しく解説していきます。
胃腸炎
下痢や嘔吐などの胃腸炎の症状が現れると、腸内環境が乱れ、有害な菌が支配的になることがあり、それに伴っておならの臭いが強くなることがあります。
この場合、おなかの中でガスが発生するため、お腹が張った感じや腸からゴロゴロ、キュルキュルといった音が聞こえるケースもあります。
腸閉塞
腸閉塞は、何らかの原因により腸が塞がっている状態のことです。閉塞の程度によっては重症化し、短期間で危機的な状況に陥ることもありますので、注意が必要です。
腸閉塞の症状には、おなら以外に食欲不振、嘔吐、便秘、下痢があります。
とくに何か異物を飲み込んでしまったかもしれないという時に、これらの症状が見られた場合にはすぐに動物病院を受診するようにしましょう。
膵外分泌不全
膵臓からは、さまざまな栄養素を分解する消化酵素が分泌されます。この消化酵素がほとんど分泌されなくなる病気を、膵外分泌不全といいます。消化がうまく行われず、小腸による栄養吸収ができないことで、おならが臭くなります。
膵外分泌不全の症状には、白い脂肪便や軟便、食欲はあるが体重が増えないなどがあります。
犬のおならが臭い時の対処法
愛犬のおならが臭いと感じた際には、適切な対処が必要です。具体的には、以下の対処法が考えられます。
- 体調や食欲が問題なさそうであれば様子をみる
- 異常が見られればすぐに動物病院を受診する
それぞれの対処法について、詳細を見ていきます。
1. 体調や食欲が問題なさそうであれば様子をみる
下痢や軟便、嘔吐などの消化器症状がなく、「元気があって食欲もあるのにおならが臭い」といった場合は、以下の方法を試しつつ、様子をみるのも良いでしょう。
1-1. フードの銘柄を変える
腸内の未消化物が醗酵することで悪臭のガスが発生しますので、良質で消化の良いフードに変えてあげると良いでしょう。
高タンパク質なご飯が消化不良の原因となる場合もありますので、注意が必要です。
1-2. 早食いを防止する
早食いをすることで、空気も一緒に食べてしまう犬の場合は、早食い防止用のフードボウルを使うなど、ゆっくり食べてもらうように工夫しましょう。
1-3. 水分を多く摂る
便が腸内に長時間滞留すると、悪臭のするガスが発生することがあります。そのため、便秘を予防することはおならの臭いを抑えるためにも重要です。
便秘予防のひとつとして水分摂取が有効です。
ヤギミルクや出汁などで香りづけをする、フードをふやかしてみる、茹で野菜を足す等、是非試してみてください。
1-4. ストレスを軽減する
ストレスが溜まってしまうと、消化管の動きが低下して、腸内細菌のバランスが崩れ、悪臭のガスが発生することもあります。
ストレス解消のためにも定期的な散歩や運動、飼い主さんとのスキンシップを行うようにしましょう。
2. 異常が見られればすぐに動物病院を受診する
おならの中には、病気が関わっているものもあります。
おならの回数が急に増えた、臭いが強くなった時には、あわせて食欲不振になっていないか、下痢や軟便が起きていないか、便の色に変化がないかも確認しましょう。
また、腸閉塞や重度の腸炎では、お腹の痛みがあり、動かなくなる、触れられるのを嫌がるといったことがあります。
このような場合には病気が関わっている可能性がありますので、様子を見ず、早めに動物病院を受診することが望ましいでしょう。
臭いおならは「腸内環境の乱れ」が原因
過剰なタンパク質や脂肪、食物繊維、アレルゲン原料を抑え、和漢植物で胃腸に栄養補給するドッグフード。 脂質など体に不要なものをも燃やして鎮めるサプリメント。
胃腸トラブルにオススメのフードはこちら
◆和漢みらいのドッグフード 特別療法食IC (胃腸・消化器用)
◆和漢ペットサプリ 燃焼プラス
まとめ
犬のおならは腸内の状態を反映するひとつのサインですが、基本的には生理現象ですので、あまり気にしなくて良いケースがほとんどです。
ただし、おならのにおいが異常に臭かったり、発生回数が異常に多かったりする場合、これは病気の一つの症状として現れることがあります。おなら以外でも、食欲や排便の変化、その他気になる症状が見られる場合も、動物病院で専門家を受診しましょう。
<おならの原因となる腸内環境を乱す5つの原因>
①食べ物 ②ストレス ③興奮 ④老化 ⑤病気<おならが臭い時に考えられる病気>
・胃腸炎 ・腸閉塞 ・膵外分泌不全<対処法>
■様子を見る
・フードの銘柄を変える ・早食い防止 ・水分を多くとる ・ストレス軽減■病院受診
・急な変化、食欲不振、下痢や軟便などがあったら病院を受診する